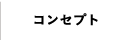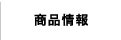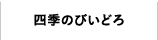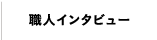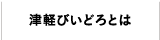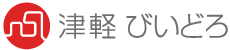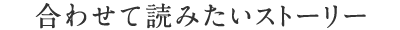『津軽びいどろ』の生まれた青森県の多彩な「いろ」と「ひと」と「もの」、そして「こと」を訪ねて取材、土地の魅力を発信していくコンテンツです。今回は青森には欠かせないもの「りんご」について、家族でりんご園を営む相馬澄佳さんから、りんごづくりについてと、生産者目線での魅力についてうかがいました。
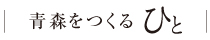


弘前で3代続くりんご農家、
相馬さんに聞いた“りんごの秘密”。
「15人に1人は何らかのカタチでりんごに携わっている」といわれる、青森県弘前市。かつて城下町として栄えた街中を少し入ると、明治以降の武士たちが“刀を鋏に持ち替えて”開墾したりんご畑が、見渡す限り広がります。春には薄紅色をしたりんごの花が甘い香りをおこし、秋には赤や黄色、約200種のりんごが実る弘前。暮らしの中にりんごがあるのではなく、りんごの中に暮らしがある…。そんな場所だからこそ知ることができるりんごの魅力を、3代続く「相馬克彦りんご園」で未来の4代目を担う、相馬澄佳さんにうかがいました。
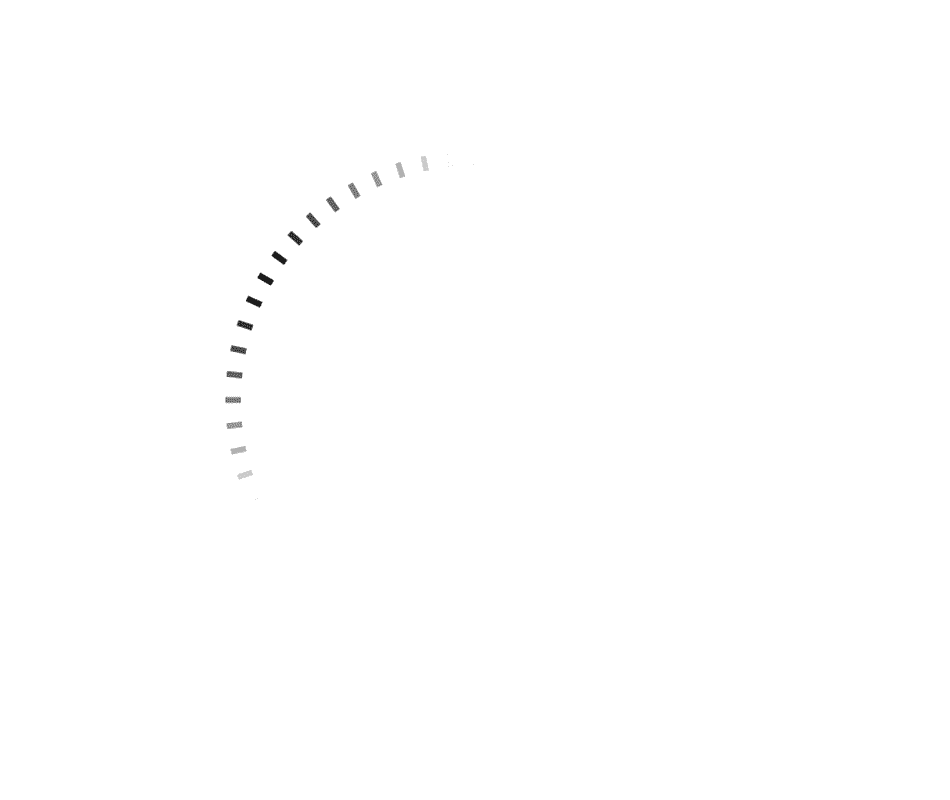
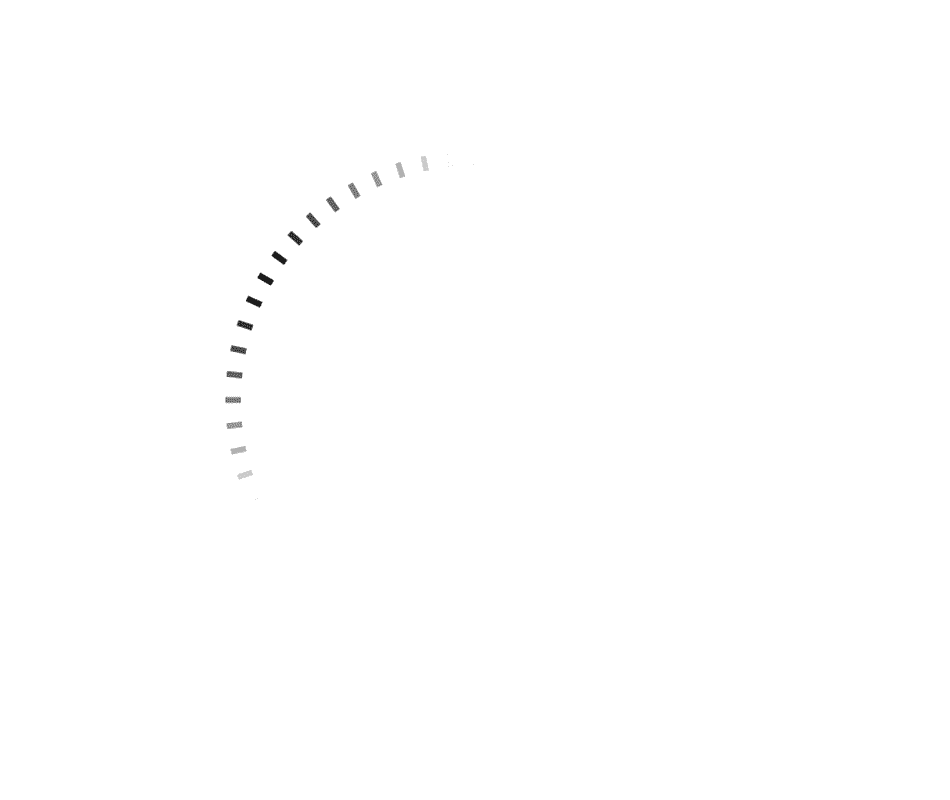
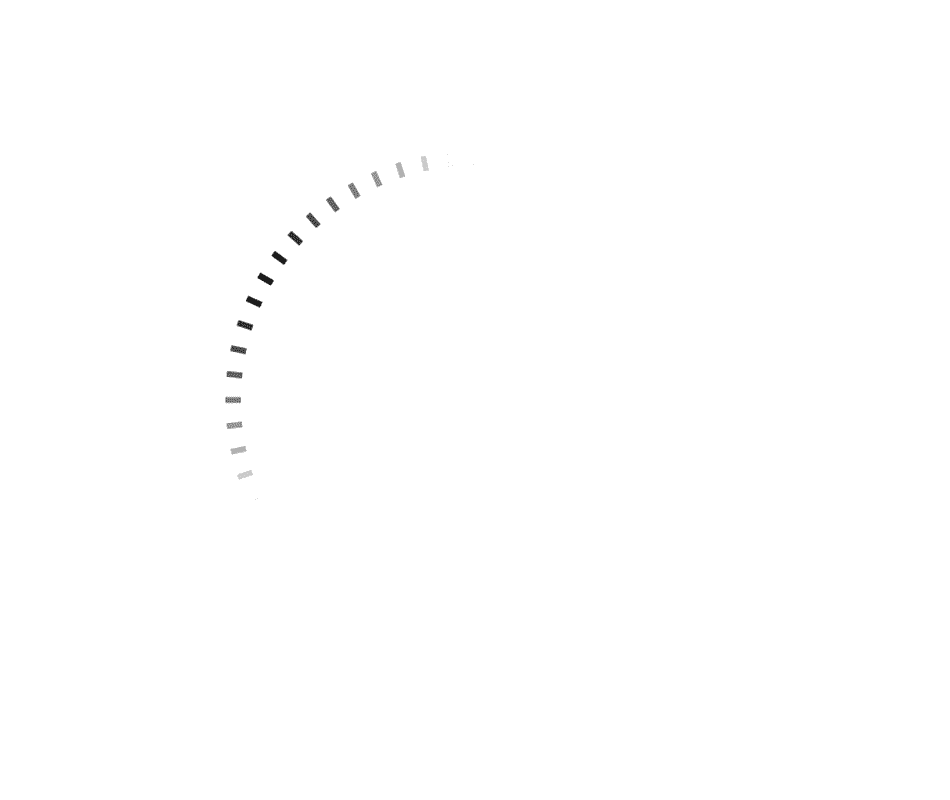
絶景を知るりんご
きらきらと広がる水田
美しい岩木山の姿
うつりかわる空の色…
そのなかで、りんごは実る
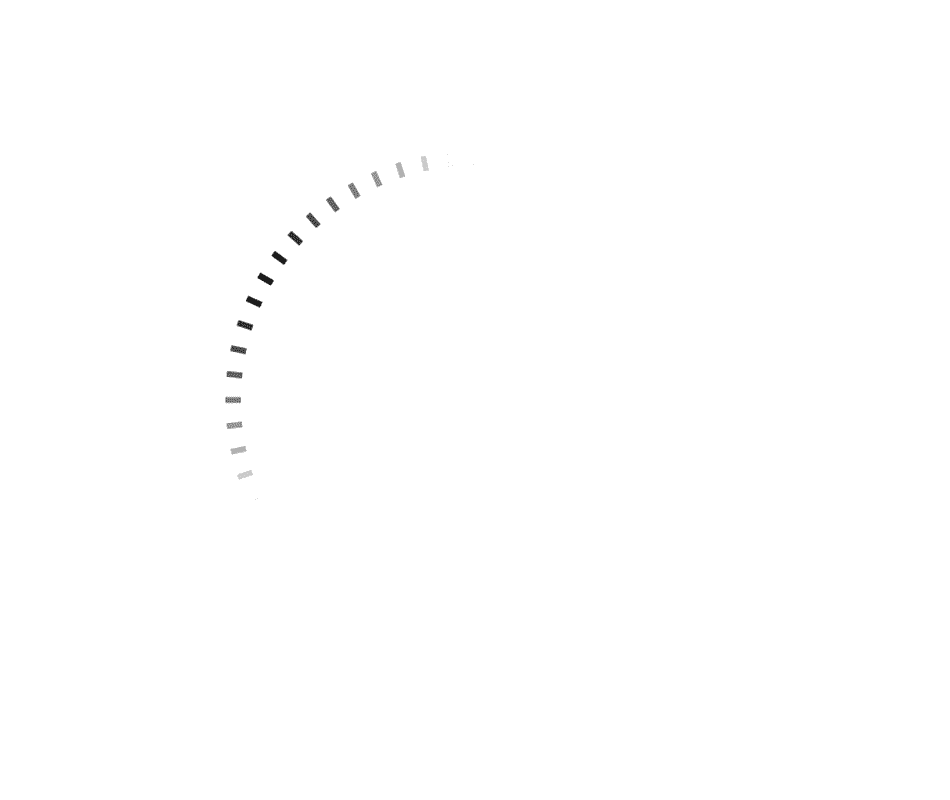
冬からはじまる、りんごづくり。
不思議な樹、りんご。
「りんご農家といえば、真っ赤に実ったりんごを収穫するイメージが大きいと思いますが、りんご畑の仕事はいろいろあって、1年中、毎日畑で過ごしています」。
樹でブランコをして、木箱で勉強をして。りんご畑とともに育ったという澄佳さんは、実家のりんご園を継いで4代目となるため勉強中の生産者さんです。
「機械化が進んでいる作業もありますが、りんごは人の手でしかできない作業がほとんどなんですよ」。
りんごは収穫までに必要な作業が大きく7つあり、一つひとつの作業をどれだけ丁寧に・的確に行うかによって、見た目も味も大きく変わってしまいます。肥料をあげたり薬をまいたりといった作業も、状況に合わせて判断しなければいけません。身近な果実ながら、実は収穫がとても難しい果実。それがりんごなのです。
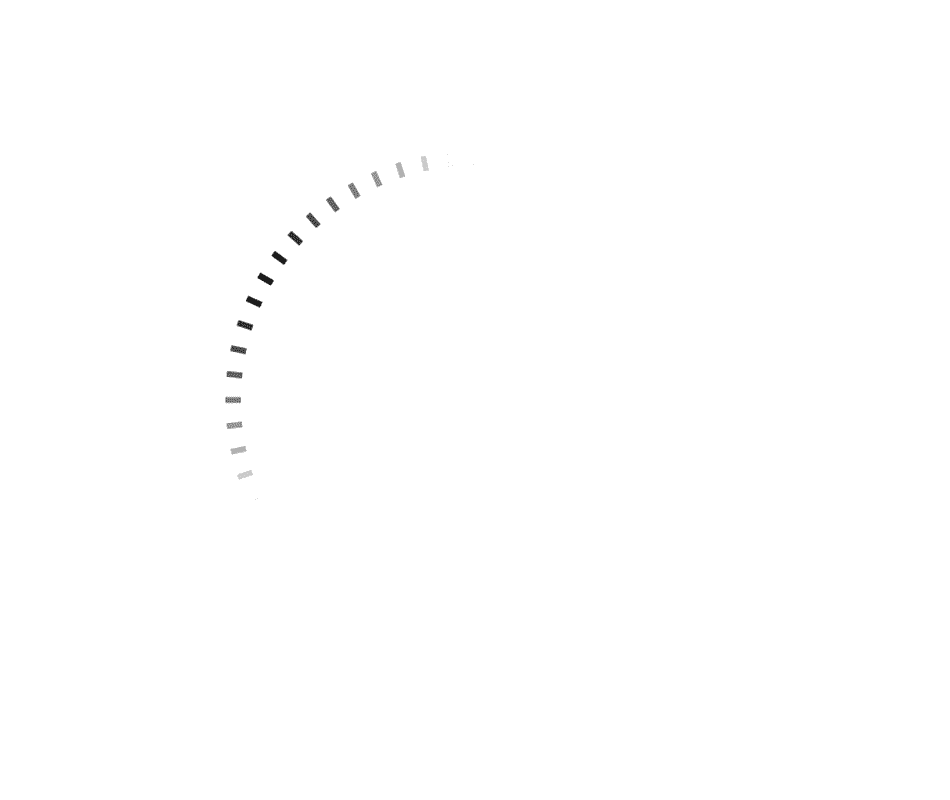
りんごづくりがスタートするのは、雪の降る12月〜1月頃。「枝伐り」といって、陽あたりや作業性を考慮しつつ、伸びた枝や新しい枝を剪定することからはじまります。青森のりんごの樹は低く剪定するのですが、そうすることで陽光が充分にあたり、栄養が実にまわって美味しくなるのだそうです。
5月に花が咲くと、花が咲いている1週間の間に「授粉」の作業があります。「受粉」には蜂のチカラも借りるのですが、雌しべへ均等に花粉をつけなければ丸く大きな実にはならず、花の一つひとつに花粉をつけていくのは、ほとんどが農家のかたの手作業。キレイで美味しいりんごには、人の手が欠かせないのです。そうして授粉が終わると、次は「摘花」「摘果」の作業となります。りんごはひとつの株に5つほど花が咲くものの、すべてを実にすると栄養が足りなくなってしまうので、必要なもの以外は摘みとってしまうのだとか。花を摘む場合は「摘花」、未熟な実を摘む場合は「摘果」と呼ばれています。
また、おもしろいのは、りんごは「同じ品種の花粉では実がならない」こと。周囲に別品種を育てるりんご園があれば自然受粉を待つ場合もありますが、相馬さんの園では、必ず違う品種の樹を一緒に植えているそうです。小さな実の成る受粉用の品種が“接ぎ木”されている樹もありました。
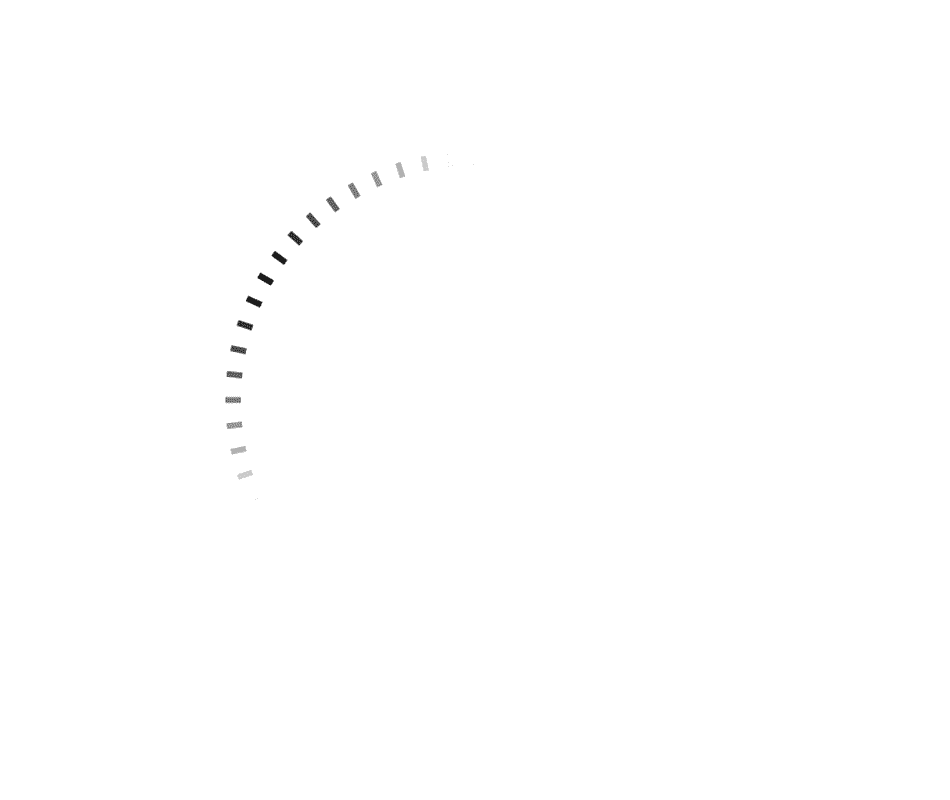
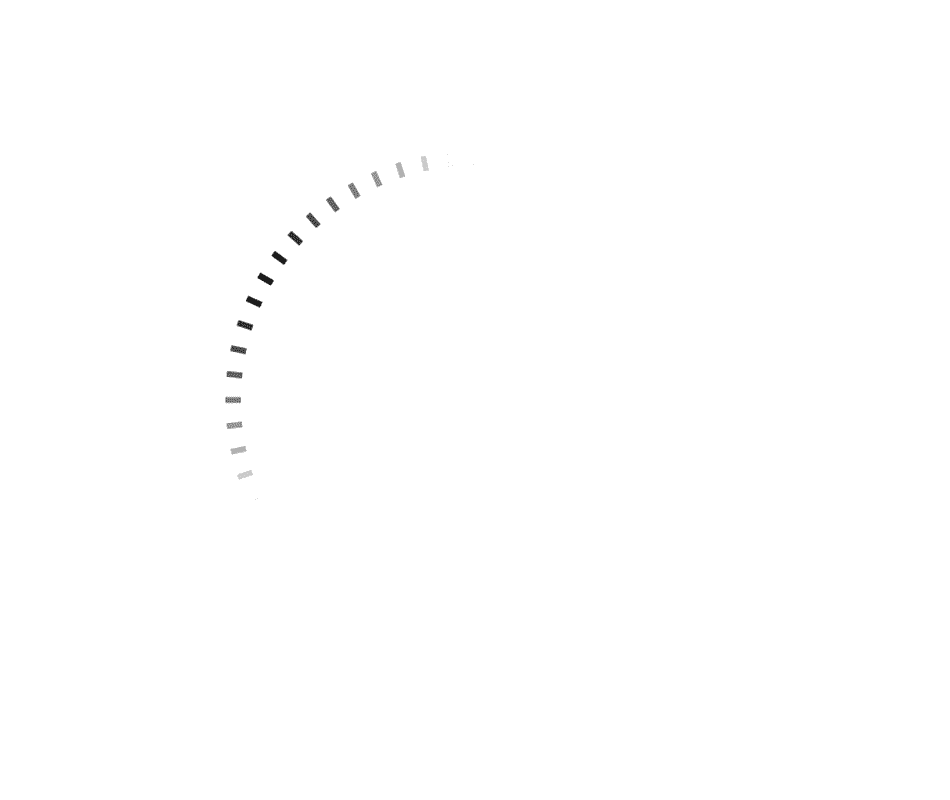
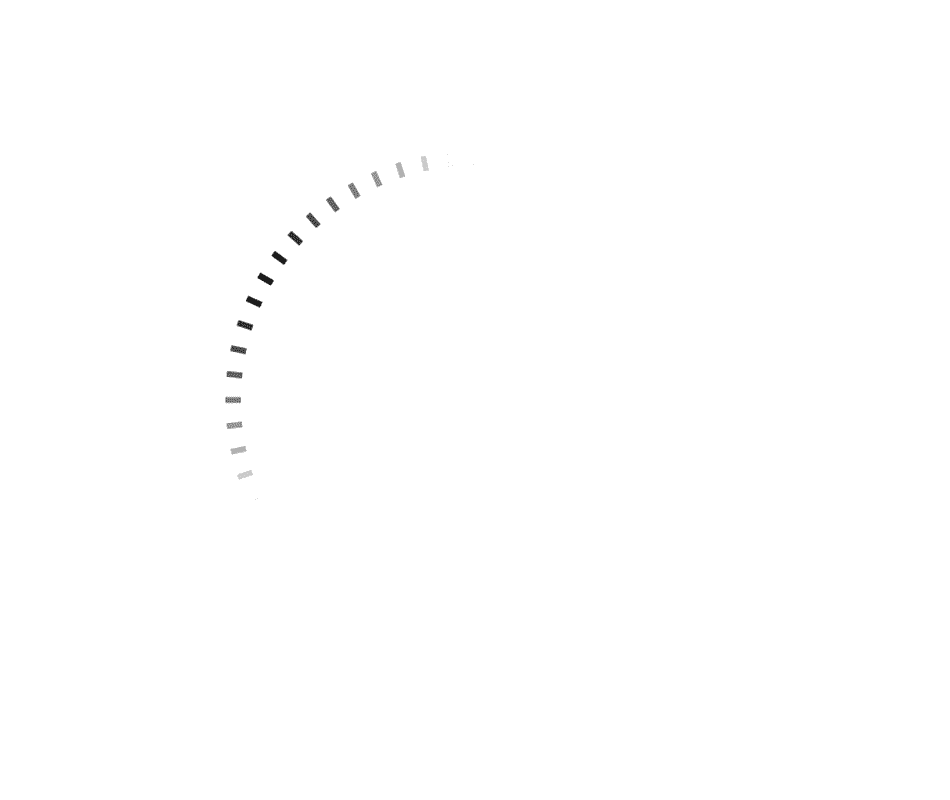
葉を残して甘くする、
相馬克彦りんご園の「葉とらずりんご」。
花が実を結ぶと、品種によって「袋かけ」の作業がはじまります。りんごの実は収穫までなるべく光に当てないほうが、美しい赤色になるからです。赤い品種、とくに「ふじ」は、この美しさが品質の高さに繫がります。
「うちの園のだと、ふじの樹に10万枚くらい袋をかけます。私は1日に2000枚くらいですが、ベテランになると5000枚くらいかけられるんですよ」。
そうして9月頃に袋をとると「葉とり」の作業に入ります。赤い品種は陽が当たることで色づくため、実にかかる葉っぱを取っていく作業です。ただ、相馬さんの園では、あまり葉を取らずにりんごを育てています。葉を残すとたくさん光合成ができて、甘みや美味しさが増すからです。枝が混んでいる所や、実に葉がくっついている所など、必要なところだけ見極めて葉を取っているのだとか。真っ赤な実に白い葉っぱの影ができることもありますが、その美味しさが話題となり、最近は「葉とらずりんご」として青森の人気商品となっています。
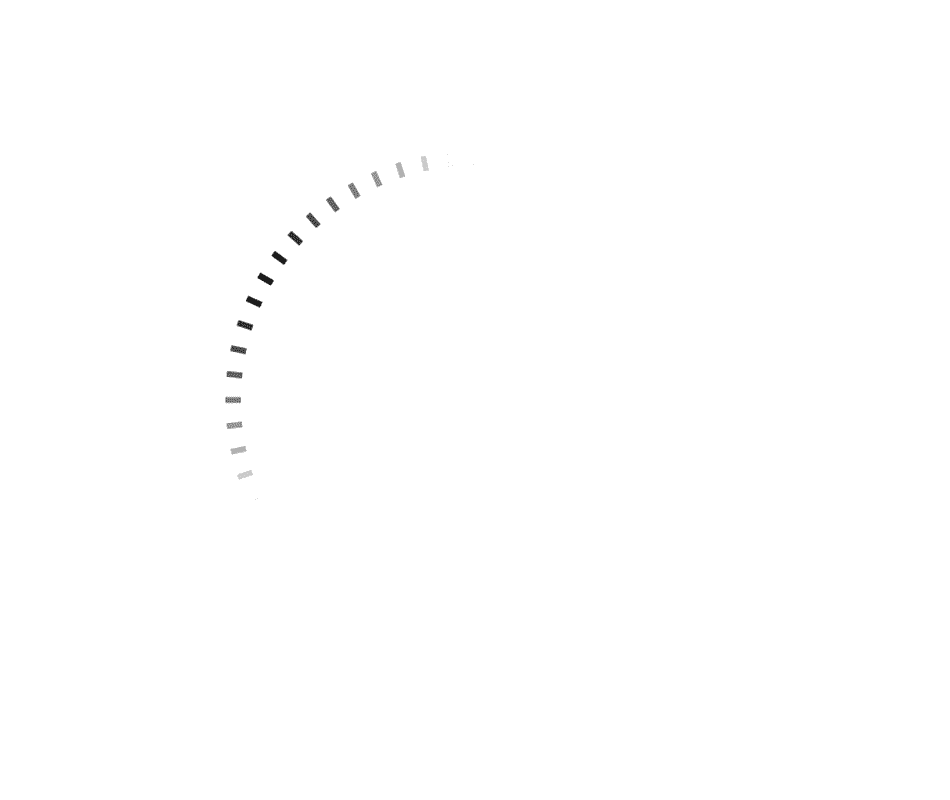
そして、いよいよ秋。ほかの品種の作業と並行して「ふじ」は「玉回し」の作業に入ります。これは枝になる実を一つひとつ回してまんべんなく光に当てる作業で、私たちが撮影に伺ったのがちょうど「玉回し」のころでした。目の前に広がる、豊かに実ったりんごたち。そのすべてを太陽の方向へ少しずつ回して、ぐるりと赤くする…そんなに細やかな作業がることに、純粋な驚きがありました。
収穫は品種によって差がありますが、11月には収穫のピークを迎えます。1年間、たえず手間をかけながら育てたりんごが、こうしてやっと出荷となるのです。相馬さんのりんご園で出荷される、約40万個のりんごたち。その数を、ご家族5人とお手伝いの方5名でやりきるのは、簡単なことではありません。どの作業も、その年の気候や樹の状態によって見極めが必要ですし、正解というものがない職人仕事です。
「りんごは“樹を1000本伐って一人前”、経験からしか学べないことが多いんです。だからこそ、技術を途切れさせないことが大切だなと感じています。いまはほかの農家さんと協力し合って、先輩や大先輩たちに教わりながら、みんなで技術を繋いでいこうとしています」。
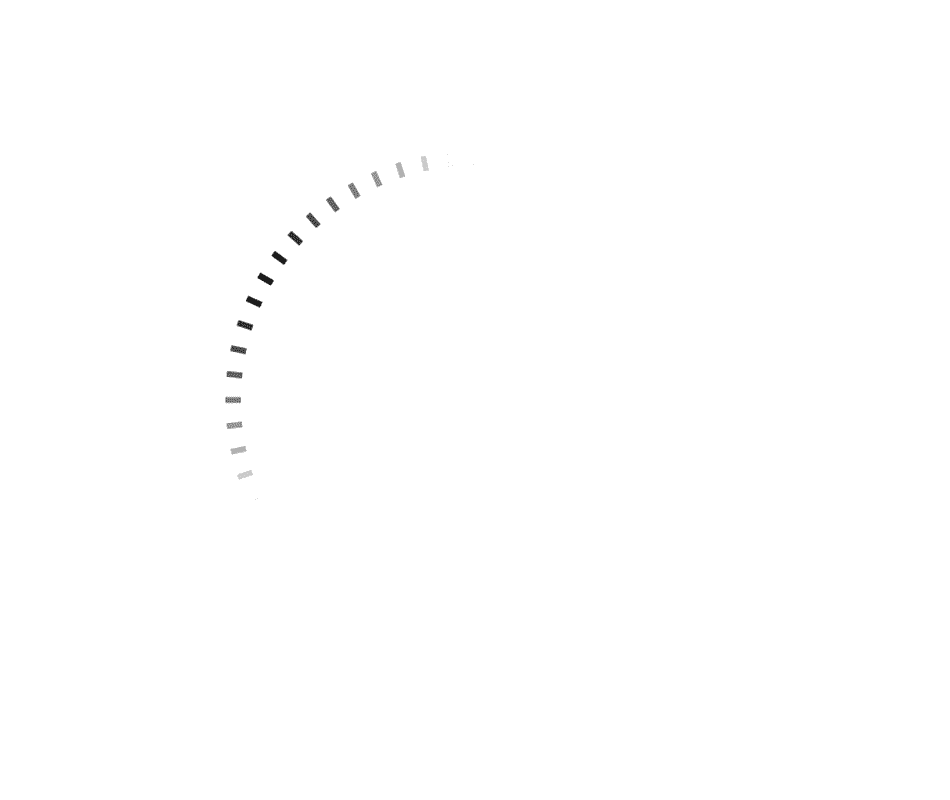
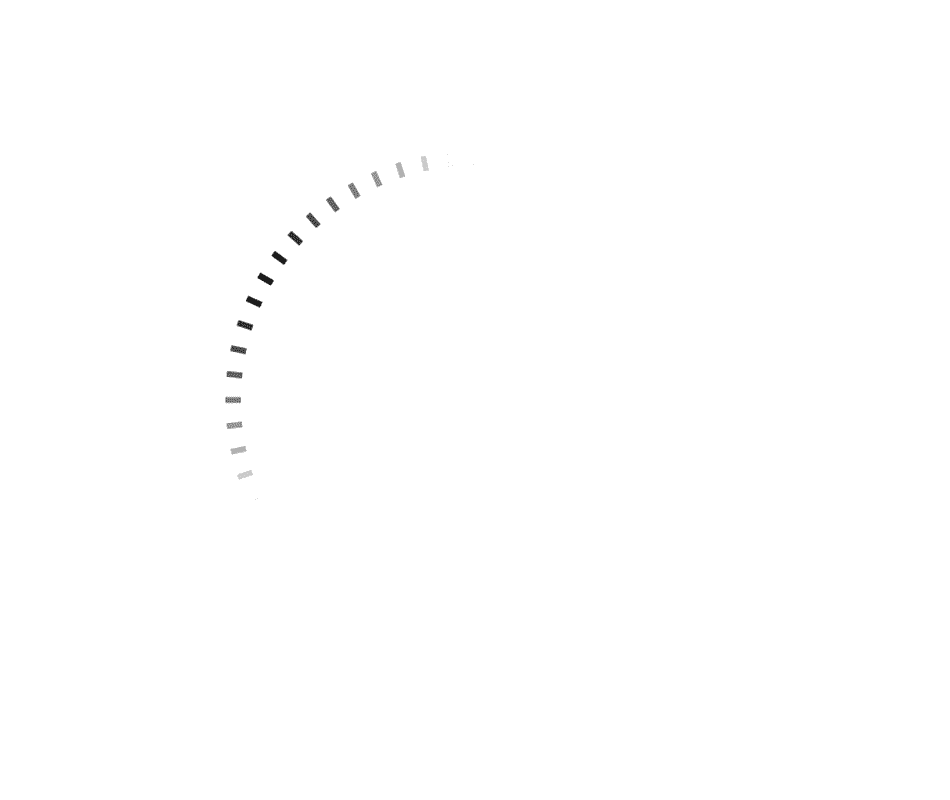
その名も「スターカット」
りんごを輪切りにしてみたら
真ん中が星みたいで可愛くて
皮までマルっと食べやすい
農家直伝の切り方
消費者目線で“みんなが笑顔になるりんご”づくりを
澄佳さんは大学4年生から3年間「ミスりんご」として活躍した経験を活かして、現在はSNSを中心に情報発信にも力を入れています。
「りんごづくりの楽しさや作業風景、家族で営むりんご園の様子。もっとりんごの魅力を知ってもらいたくて、私にできる発信をはじめました。やっぱり農家の数は減っていますから、誰かの心に響いて、りんごをつくる人が増えてくれたら良いなと思っています」。
ミスりんごとしての活動では、日本全国を飛び回りながらりんごの魅力を発信していた澄佳さん。交流を通じて“食べる人の目線”を知るなかで、地域によって好まれるりんごの味が違うことや、購入方法・購入個数の違いに気づいたのだそうです。
「畑の中にいると、生産者の目線になってしまいます。私の目標は、食べて美味しく、見て可愛い、家族団らんの中心にある“みんなが笑顔になるりんごをつくること”です。食べてくれる人の目線で販路の開拓や商品開発をしながら、りんごの可能性を広げていきたいです」。
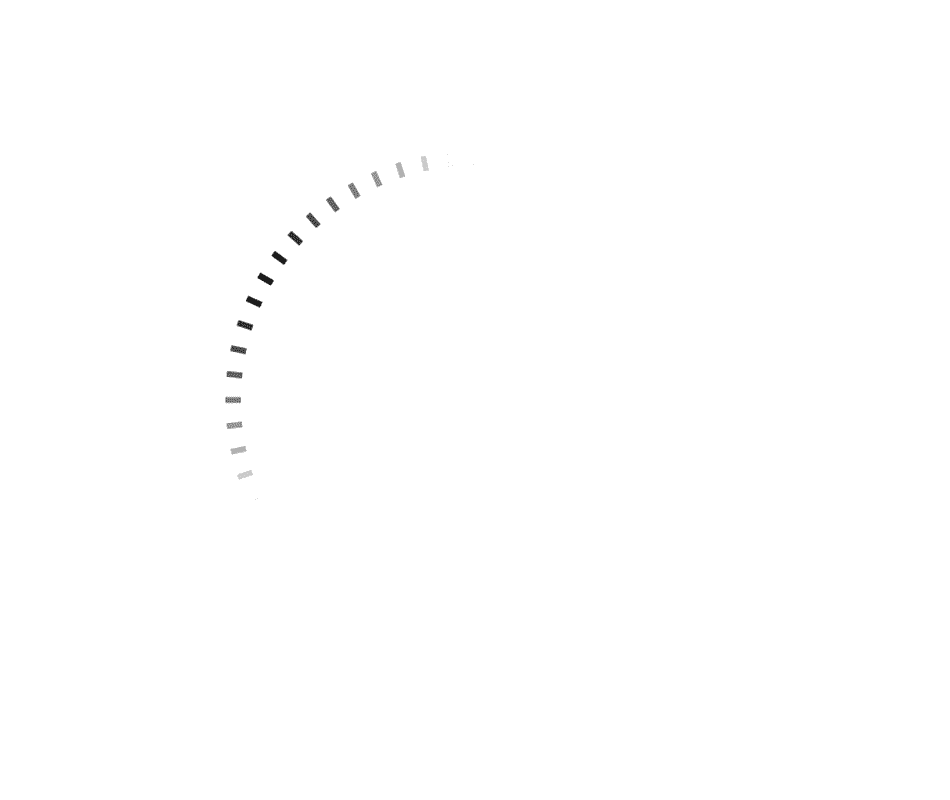
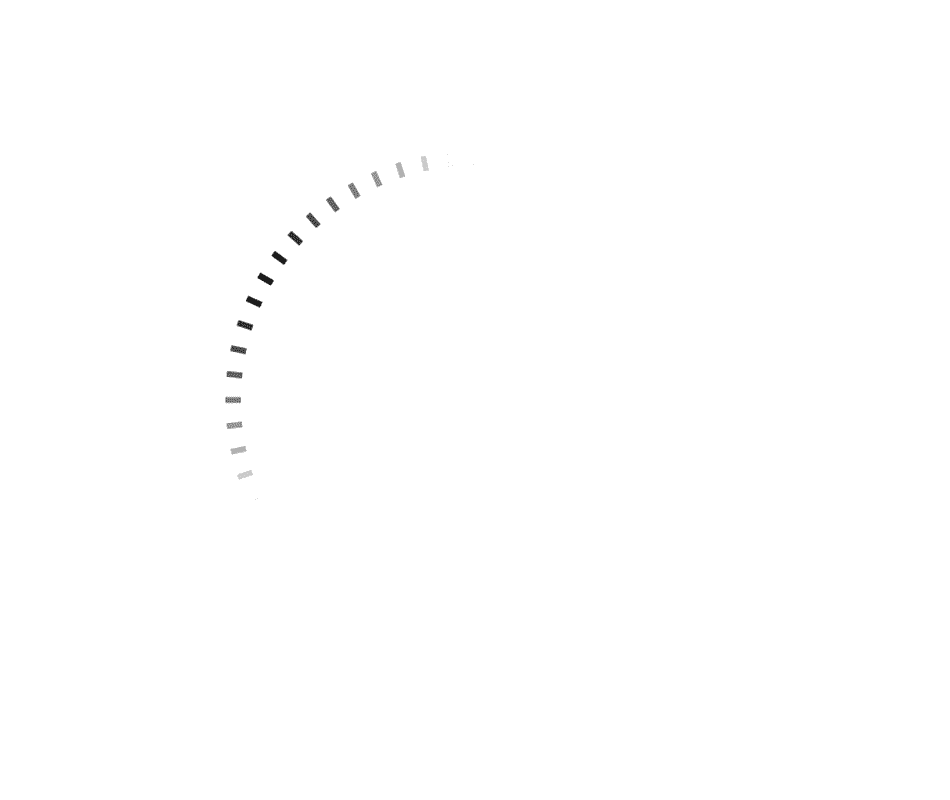
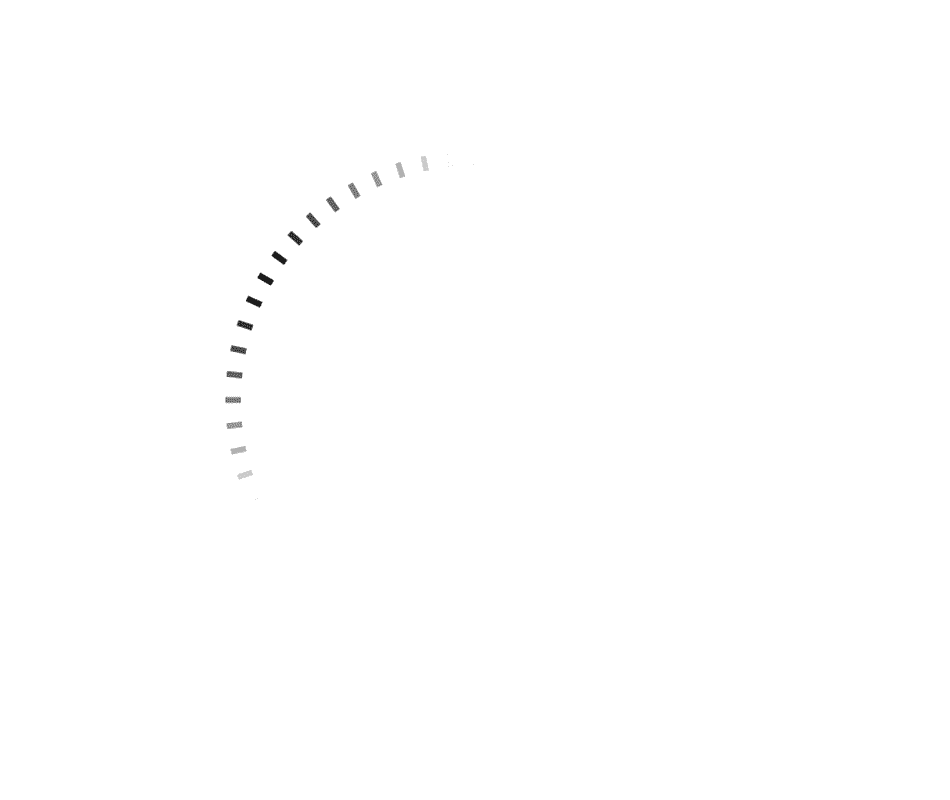
りんごづくりを通じて、
青森へ恩返しができるように。
「私が本格的にりんご園を継ぐと決めたのは、自然災害に見舞われたときです」。
“いつかは継ごう”と考えて、大学で農業を学んでいた澄佳さんが目にしたのは、雹で傷だらけになってしまったりんごと落胆した家族の姿でした。
「もう絶対に悲しませたくない、私がやろう、と思いました。このときは、シードルをつくっているkimoriさんやA-FACTORYさん、いろんな方に助けて頂いて…。ダメになったりんごを、廃棄することなく生かすことができました。いまも、りんごジュースやジャムの商品開発をしています。この恩を、青森のりんごを盛り上げていくことで返していきたいんです」
SNSやイベントを通じて、精力的に発信を続けている澄佳さん。彼女の素敵な発信は、りんごへの愛情とユーモアに溢れていて、見ているだけで明るい気持ちになれます。四季折々のりんご園や、畑から見える美しい風景も必見です。普段何気なく手に取っているりんご。その向こう側の景色を、ぜひのぞいてみてください。
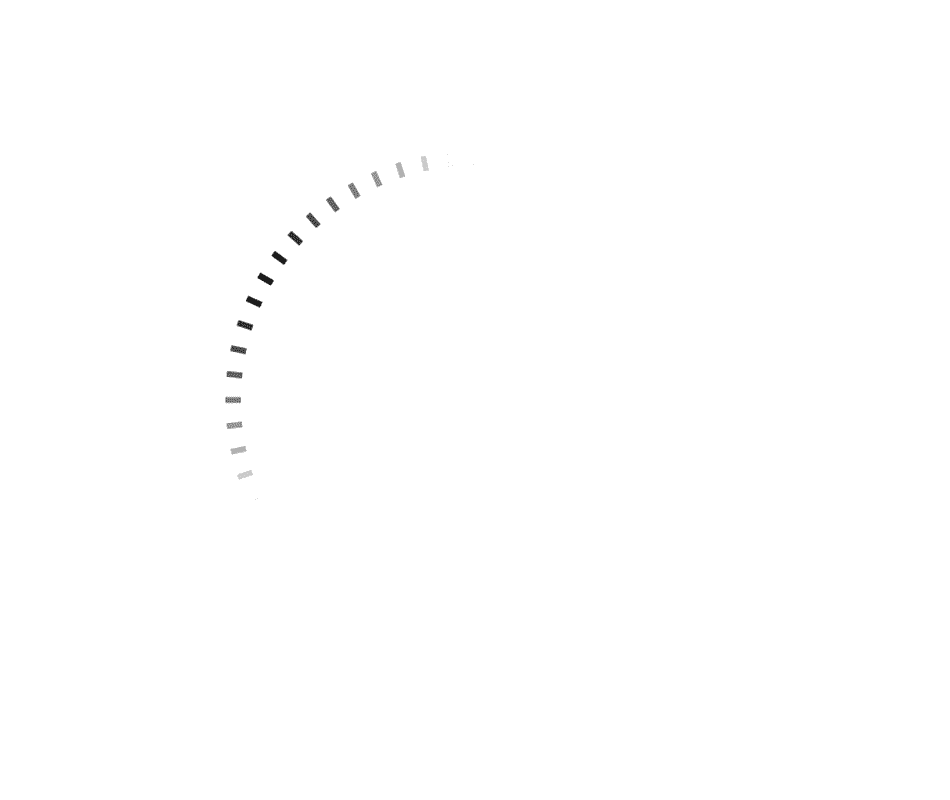
ギャラリー
今回の取材でお話をお聞きしたのは...

相馬克彦りんご園
りんごづくり一筋、青森県弘前市で、親子3代で営むりんご園。6ha、15種類のりんご栽培に取り組み、70年以上の歴史を紡いでいます。こだわりは、落下ぎりぎりまで成熟させてから収穫する「樹上完熟」と、日光を充分に当てて、葉を取り過ぎない「葉とらず栽培」。昼夜の寒暖差が大きい環境で育つ、糖度の高いりんごが人気です。