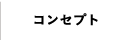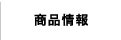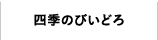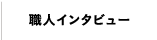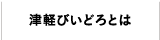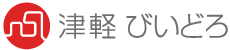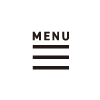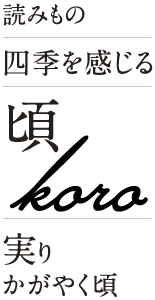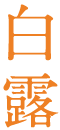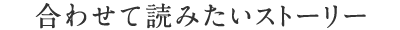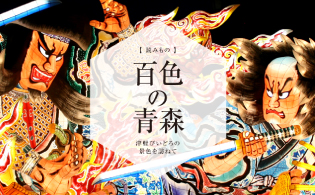夏の暑さが和らいで、朝夕がぐっと冷えこみ、草花のうえに小さく露が結ばれる頃。9月7日ほどから秋分までの間を二十四節気で白露と呼びます。“白”は陰陽五行では秋の色とされていて、秋がかたちとなって見える頃、ともいえます。水田では垂れた稲穂が黄金色に輝く光景が美しく、米農家では作業のピークに。また、収穫と同時に台風が多い時期でもあるために、日本の農作業の目安となる雑節では、この時期に起こりやすい自然災害を警戒する農家三大厄日「二百二十日」を迎えます。秋の実りに感謝しながらも、自然と向き合い、その厳しさに備えて克服するための時間が白露なのです。




白露の頃は日中に暑さが残るものの気候が良く、スポーツや外での活動が増えていく一方で、季節の変わり目として体調を崩しやすい時期でもあります。そのため古来日本人は、豊かな旬の味覚で栄養を補うほかに、「重陽の節句」で家族の厄除と長寿を祈ってきました。重陽の節句は9月9日、陽の数字(奇数)のいちばん大きな数が重なる日にあやかる行事です。厄除の象徴とされていた菊の花を、お酒に浮かべたり枕に入れたりすることで、この時期を乗り越えようとしたのでしょう。現在でもお刺身などには黄色の菊が添えられていますが、実際に、食用菊には殺菌作用があるのだとか。見た目にも華やかな古来の知恵を、この秋に取り入れてみてはいかがでしょうか。