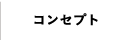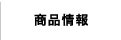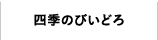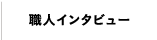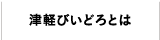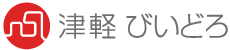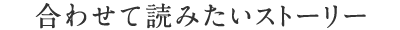【読みもの】びいどろと巡る、みちのく酒語り 秋田編みちのくの風土を地酒から感じる酒器旅

第4回秋田酒類製造株式会社
-
秋田酒類製造株式会社
秋田県秋田市川元むつみ町4-12

寒の入りを迎え、いよいよ本格的な冬将軍が到来した1月の秋田。吐く息は白く染まり、夜には星も凍てつきそうな静寂に街は包まれます。人々が、かまくらの柔らかな灯りに心寄せるこの季節。そんな北国の風景のなかで、土地に根ざし酒を醸す人たちには、その場所でしか語れない物語があります。本連載では、日本酒ライター・関友美が、『津軽びいどろ』とともに各地の蔵を巡り、酒の背景と魅力をたどります。
これまで青森県の12蔵を訪ねてきましたが、今回はお隣・秋田県へ。第4回は県都・秋田市で『高清水』を醸す『秋田酒類製造』を訪ねました。

秋田の風土に根ざした、
3つの酒蔵。
秋田県秋田市は、日本海に面した、自然豊かな土地です。奥羽山脈からの清らかな伏流水と、冬のきりりと冷たい空気に恵まれています。古くは日本海を行きかう北前船(きたまえぶね)が立ち寄る港町として栄え、米どころ秋田平野を背景に、お酒や味噌などの発酵文化が深く根づいてきました。
この地に蔵を構える『高清水』には、それぞれに大切な役割を担う、3つの酒蔵があります。
本社のある秋田市川元むつみ町には、高清水のお酒の多くをささえる屋台骨「本社蔵(千秋蔵)」があります。1978年にできた6階建ての蔵は、最上階に運ばれたお米が、工程ごとに下の階へおりてくる、合理的な造りになっています。
そして、その隣に静かにたたずむのが、「酒造(さけ)道場」をコンセプトにした手づくりの小さな蔵「仙人蔵(せんにんぐら)」です。ここは、あえて最新の設備を排し、蔵人が「日本酒とは、何か。秋田の酒づくりとは、何か」を学ぶための修行の場。全国の品評会に出すような特別な一本が、ここで大切に育まれます。「通い徳利」など古い道具が展示されているギャラリーの2階からは、その静謐な空間をガラス越しに垣間見ることができました。

最後に、本社から12キロほど離れた場所にあるのが「御所野蔵(ごしょのぐら)」です。昔ながらの技を大切にしながら最新の温度管理なども取り入れ、主に「吟醸酒(ぎんじょうしゅ)」という華やかな香りが特徴のお酒などを、ていねいに造っています。
どっしりと構える千秋蔵。技を磨き、未来を見つめる仙人蔵。伝統と新しい技術をつなぐ御所野蔵。この3つの蔵が、それぞれの個性を響かせあうことで、『「高清水」』という、ひとつの豊かな味わいを奏でているのです。

蔵人たちの手づくり。
秋田の巨人『高清水』の、
温かい素顔
秋田の酒といえば、多くの方が思い浮かべる『高清水』。
かつて東京・高円寺の環七通り沿いにあった看板や、今もモノレール浜松町駅のホームで目にするその名に、「昔からある大きな蔵」という印象を持つ方も少なくないでしょう。県内有数の生産量を誇るその姿から、誰もが最新の設備による効率的な酒づくりを想像するはずです。私も、そうでした。
しかし、そのイメージは千秋蔵を訪れたことで根底から覆されます。そこには私たちの想像をこえるほど、人の温もりにあふれ、そして、少しばかり「常識はずれ」とさえ思えるほど手間ひまをかけた酒づくりの物語がありました。

ふるさとを想う心が、
東京に届けた秋田の味
『高清水』というお酒を深く知るには、ただ“大きな酒蔵”というだけではない、その背景にある温かい物語を知ることが大切です。
かつて東京で秋田のお酒が広く親しまれるようになったのは、ふるさとを離れ、首都圏で懸命に働いた、たくさんの人たちがいたからでした。高度経済成長の時代、“金の卵”と呼ばれた集団就職の若者や、ふるさとに家族を残し働きに出た人たち。慣れない土地で働く彼らが何よりも求めたのは、心なごむ「ふるさとの味」でした。
「秋田のお酒を置いてほしい」。
そんな声が町の酒屋さんへ届くと『高清水』、『爛漫』や『太平山』、『天寿』といった秋田を代表するお酒が次々と東京の店頭にならぶようになりました。

もともと「秋田酒類製造」の設立は、太平洋戦争さなかの1944年。当時の企業整備令に基づき、地域の24の酒造家が集まって設立され、その後12の蔵に集約されて現在に至る、という歴史があります。
そうした時代に翻弄されながらも、集約された技術と生産力があったからこそ、東京で高まる需要に、応え続けることができたのです。
日本が復興へと向かう活気あふれる時代。ふるさとを離れて働く人たちにとって、仕事の終わりに味わう一杯は、遠い故郷を思い出させる、心安らぐひとときだったのでしょう。高清水は今も、そうした温かな記憶とともにある酒蔵です。

受け継がれる
酒づくりのこころ。
今回お話を伺ったのは、高清水の屋台骨である「本社蔵」を率いる、杜氏の菊地 格(きくち ただし)さんです。
菊地杜氏は、東京農業大学の醸造学科を卒業後、地元・秋田で働きたいという想いから、昭和62年(1987年)に秋田酒類製造へ入社しました。穏やかで、誠実に語る姿に、実直な人柄がにじみ出ています。入社後はまず研究室に配属され、その後、精米工場を経て、2015年に本社蔵の杜氏に就任。その歩みは、奇しくも偉大な先輩の背中を追うような道のりでした。
菊地杜氏にとって、道標のような存在といえるのが、御所野蔵の杜氏を務める加藤 均(かとう ひとし)さんです。『高清水』は全国新酒鑑評会で通算25回(※2025年12月時点)の金賞受賞を誇りますが、その礎を築いた中心人物こそ、まさに「現代の名工」と称される加藤杜氏なのです。「私が入社した当時、加藤杜氏もまだ本社蔵(千秋蔵)におりまして、一緒に仕事をしていました。尊敬する先輩なんですよ」と、菊地杜氏は誇らしげに振り返ります。

その加藤杜氏の経歴は非常にユニークです。大学時代に打ち込んでいたのは、酒づくりとは全く異なる分野の研究でした。しかし卒業後、縁あって未経験から高清水に入社し、研究室に配属されます。転機となったのは、吟醸酒ブームの中で計画された精米工場の建設・立ち上げでした。その経歴を買われ、加藤杜氏が担当に抜擢されると、独学でこれをやり遂げ、ついには吟醸蔵「御所野蔵」の設計から醸造まで一任されることになったのです。
しかし、新しい蔵での酒づくりは一筋縄ではいきませんでした。データさえあればある程度美味しい酒は造れる、という考えが、大きな間違いであると気づかされることになります。
なぜならば、新しいコンクリートの蔵には、酒造りに重要な目に見えない酵母や微生物といった「蔵の空気」、いわば「聖域」がまだ出来上がっていなかったからです。
その後、それらが整うまでには、実に10年近くかかったといいます。

科学の限界を知り、目に見えない自然の偉大さを痛感した加藤杜氏。しかし、この経験こそが、科学的なアプローチと伝統的な技を高い次元で融合させるきっかけとなりました。こうした科学と伝統の往還が、高清水が時に業界を驚かせるような革新的なお酒を生み出す土壌となっているのです。例えば、独自技術で熟成香とフレッシュな味わいを両立させた「加温熟成解脱酒(かおんじゅくせいげだつしゅ)」もその一つ。伝統を守るだけではない、高清水のもうひとつの顔です。

伝統的な技の系譜を受け継ぎながらも、研究者としての知見と、未経験から道を切り拓いてきた粘り強い探求心を持つ加藤杜氏。その背中を見てきたのが、現在の菊地杜氏です。最盛期に比べて生産量が落ち着いた今の状況を、菊地杜氏は冷静に見つめています。「生産量が多かった頃に比べ、今は一本一本により手間をかけられるようになりました。その分、お酒の品質はさらに良くなったと感じています」。先輩が切り拓いた道を、今度は品質という本質で深めていく。その静かな自信に、高清水の未来が垣間見えました。
蔵の礎を築いたのは、新政酒造にいた頃「協会6号酵母」の発見にも関わったとされる伝説の初代杜氏・鶴田百治(つるた ももじ)。その伝統の技を受け継ぎながら、科学的な知見と探求心で道を切り拓いた先人・加藤杜氏。その背中を見つめ、品質という本質を深めようとする現在の菊地杜氏。伝統と革新が人から人へと受け継がれていくその姿こそが、今の『高清水』という豊かな味わいを奏でているのだと、静かに物語っていました。
米を知り、水にこだわる。
酒づくりの原点。
高清水の丁寧な酒づくりは、その原点であるお米と水への、まっすぐなこだわりにも表れています。お酒の味わいの核となるお米。高清水は自社に精米工場を持ち、杜氏たち自らが深く関わっています。実は、菊地杜氏も、そして先輩である加藤杜氏も、この精米工場での経験が豊富です。どう磨けば、お酒になった時にどう溶けていくのか。それを知り尽くした、「お米を見極める醸造のプロ」なのです。
「蔵に届くお米の状態がわかるからこそ、その後の洗米や蒸しといった工程も、より丁寧になるんです」と菊地杜氏は語ります。

そして、もうひとつの命である水。蔵の敷地からこんこんと湧き出る軟水は、かつて秋田の藩主・佐竹候がお茶会のために汲んだと伝わるほどの、清らかな名水です。
米を知り尽くした人の技と、土地の恵みである名水。この2つが出会うことで、高清水のあの澄んだ味わいは生まれるのです。
高清水の“宝物”。
それは、蔵人たちの
手と魂が宿る場所
酒づくりの世界には、「一麹(いちこうじ)、二酛(にもと)、三造り(さんつくり)」という言葉があります。これは、酒の味わいを決める上で、何よりもまず「麹(こうじ)」が大切だという、古くからの教えです。
その麹を育てる神聖な場所が「麹室(こうじむろ)」。案内された仙人蔵の麹室は、息をのむほど立派な空間でした。壁や天井を埋め尽くすのは、節(ふし)がひとつも見当たらない美しい秋田杉。節は微細な隙間が生まれやすく、温湿度ムラや雑菌リスクにつながるため、麹室には節のない柾目材(まさめざい)が選ばれるのです。天井は高く、空気がよどまぬよう計算された、まさに理想の麹室でした。その見事な構造に感心していると、菊地杜氏から、驚くべき事実が告げられました。
「この麹室…実はうちの蔵人たちが建ててくれたんですよ。うちには、農家もいれば腕のいい大工も5、6人いるんです。冬になると毎年、こうして蔵に働きに来てくれます」

麹室は、麹菌という繊細な微生物が心地よく生育するために、完璧な密閉性と、木の呼吸による絶妙な湿度調整が求められる、極めて高度な建築技術が必要な場所です。多くの酒蔵を見てきましたが、これほどまでに立派な麹室を蔵人たちが自らの手で建てたという話は、聞いたことがありません。しかも実際に使う自分たちが、「こうしたらもっと良くなる」と知恵を出し合いながら造り上げた、世界にひとつだけの理想の場所。この手づくりの麹室こそ、高清水という蔵の、かけがえのない宝物でしょう。

しかし、物語はそれだけでは終わりません。この特別な麹室でかつて行われていたことこそ、高清水の酒づくりの凄みを物語る、もうひとつの証拠なのです。
それは、「麹蓋(こうじぶた)」という手法を、リーズナブルな普通酒にも採用していたといいます。
これは、主に鑑評会に出すような最高級の大吟醸酒に用いる、およそ効率とは無縁の手仕事。その時間も労力もかかる作業を、日々の食卓で楽しまれる最も身近な「普通酒」に、惜しげもなく注ぎ込んでいたというのです。
もちろん、時代と共に手法は変わります。現在は、蔵人の負担を軽くしながらも、麹蓋で培った丁寧な手仕事を忠実に再現できる製麹機(せいきくき)へと、その役割の一部は引き継がれました。これもまた、品質を守るためのひとつの答えなのです。『高清水』にとって、手づくりか機械かは手段の違いにすぎません。大切なのは、どの酒にも等しく最高の品質を求めるという、蔵の哲学であり、まっすぐな想いなのです。

Tsugaru Vidro selectedfor 高清水

津軽びいどろ
「青森 台付きグラス」と「盃12ヶ月コレクション」
で味わう『高清水』2種
日本酒の味わいは、器によって印象が大きく変わります。口にあたる厚みや角度といった形状だけでなく、色や質感から受ける印象が、気分や感じ方に影響するからです。たとえば、好きなピンクの器なら心がはずみ、金色の盃に注げば特別な気分で味わえるでしょう。

「津軽びいどろ」の酒器といえば、四季をイメージした鮮やかな色合いが特長です。
今回は、菊地杜氏に「この器でうちのお酒を飲んでほしい」という視点で、特にお気に入りのびいどろを選んでいただきました。そこに注がれるのは、『高清水 純米大吟醸』と『高清水 酒乃国純米酒』です。
お酒の個性を引き出す、
津軽びいどろのかたち
友美 「今回、この2つの酒器を選んでくださったポイントは、どこですか?」
菊地杜氏 「まず『高清水 純米大吟醸』ですが、これは香りを華やかに立たせたいので、この真ん中がふくらんでいて、少し口がすぼまっているタイプがいいですね」
友美 「純米大吟醸ならではの繊細な香りを、この膨らみで優しく花開かせ、すぼまった口元でしっかり受け止める。華やかな香りを味わいの重要な要素として楽しむための、まさに理想的なかたちですね。」
菊地杜氏 「はい。一方で純米酒の『高清水 酒乃国純米酒』は、香りよりもお米の味わいをしっかりと感じてほしいお酒です。ですから、こちらの細長いかたちの方が、味わいに集中できると思います」

杜氏と語る、高清水の味わい
菊地杜氏 「それから、高清水といえば“燗酒”というイメージがあるかもしれませんね。特に、生産量の約70%を占める『本社蔵』で造るお酒は、燗にして美味しいんですよ」
友美 「いいですね、お燗ですか!津軽びいどろには、耐熱ガラスの徳利(とっくり)とおちょこがあるので、湯煎はもちろん、電子レンジでも気軽に燗酒が楽しめますね」
菊地杜氏 「ええ。例えば、この純米酒がまさにそうで、初代杜氏・鶴田百治が築いた、和やかで綺麗な高清水らしい味わいを大切にしています。伝統的な6号酵母で醸した、ほどよい酸味と深みが特長で、燗にすることでその輪郭がより一層やわらかく、豊かになるんです」

友美 「綺麗な味わいの中に、しっかりとした旨味と、肴を呼ぶ心地よい収れん味、そしてキレ。まさに毎日でも飲みたくなる素晴らしい食中酒ですね。3つの蔵が醸す、個性豊かな高清水のお酒をもっともっと飲んでみたくなりました」
菊地杜氏 「毎日晩酌として愛飲してくださるお客様のためにも、定番の味を守りたい。酒づくりの相手は微生物。よく観察して、彼らがのびのびと育つ環境を整えてあげるんです。気持ち良さそうに働いてくれる姿を毎日見るのが、本当に楽しいんですよ」

高清水の本社事務所の横には、素敵なお酒がならぶショップ「倉//蔵(くらくら)」があります。また、事前に予約をすれば、スタッフの方が仙人蔵を案内してくれる酒蔵見学も可能です(どちらも平日のみ)。
もし蔵を訪れる機会があれば、その大きな建物や機械の奥にある、この記事でご紹介した造り手たちの温かい物語を思い出してみてください。そうすれば、目にする風景がより一層味わい深く感じられることでしょう。
その一杯は、秋田の豊かな自然と、酒づくりの職人たちのまっすぐな愛情が溶け合った、美しい結晶。今夜の食卓で、お気に入りの器に『高清水』をそそいでみませんか。一杯の奥から、造り手たちの静かで確かな息づかいが、きっと聞こえてくるはずです。


ギャラリー
盃12ヶ月コレクション
復刻シリーズ青森
-

- 台付きグラス
手軽に楽しめる酒器
-

- 徳利 大

- 徳利
-

- 盃 大
-

- 盃 小
購入はこちらから
[ sake writer ]

関 友美 せき ともみ
日本酒ライター/ジャーナリスト/唎酒師/日本酒学講師/日本酒品質鑑定士/あおもりの地酒アンバサダー(第一期)/発酵食品ソムリエ/シードルマスター
北海道札幌市生まれ。
酒と地域の物語を丁寧にすくいあげる日本酒ジャーナリストとして、国内外の蔵を訪ね、雑誌、業界専門誌など多彩な媒体で執筆。専門家としてBS-TBS『関口宏のこの先どうなる?!』、TBS『ニューかまー』、朝日放送テレビ『LIFE〜夢のカタチ〜』など、テレビにも出演。近年は、全国の自治体と連携した日本酒観光や商品開発支援、酒蔵のコンサルティングなども手がける。審査員としても複数の日本酒コンクールに参加。酒を通じた地方創生の一助となる活動に力を注いでいる。
- ホームページ https://tomomiseki.wixsite.com/only
- Instagram @tomomi0119seki