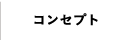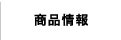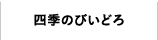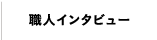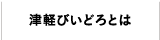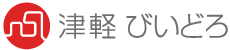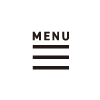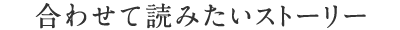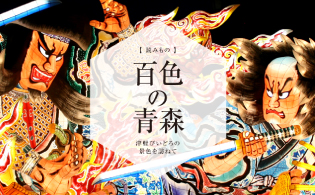【読みもの】びいどろと巡る、みちのく酒語り 秋田編みちのくの風土を地酒から感じる酒器旅

第1回株式会社 齋彌酒造店
-
株式会社 齋彌酒造店
秋田県由利本荘市石脇字石脇53

7月の秋田。田んぼでは稲がすくすくと育ち、夏の気配が少しずつ広がり始めます。そんな風景のなかで、土地に根ざし酒を醸す人たちには、その場所でしか語れない物語があります。日本酒ライター・関友美が、「津軽びいどろ」とともに各地の蔵を巡り、酒の背景と魅力をたどります。
青森県内12蔵をめぐってきた旅は、今回から秋田県へと舞台を移します。第1回は、由利本荘市で「雪の茅舎」「美酒の設計」「由利正宗」を醸す齋彌酒造店を訪ねました。

清らかな雪どけに恵まれた、秋田県・由利本荘市
秋田県南西部に位置する由利本荘市は、県内最大の面積を持ち、海沿いから山あいまで変化に富んだ風土を有しています。鳥海山の伏流水が豊富に流れ込むこの土地は、昔から日本酒、味噌や醤油などの発酵文化が根づく地域でもあります。
明治35年創業、120年以上にわたり酒を醸し続けてきた齋彌酒造店もまた、この水の恵みとともに歩んできた蔵です。裏山の新山を水源とする中硬水の仕込み水は、今も蔵の敷地から湧き出しており、「雪の茅舎」の澄んだ味わいには欠かせません。

「のぼり蔵」坂の上の蔵からはじまる美酒の物語
蔵を案内してくれたのは、専務取締役であり杜氏でもある高橋藤一(たかはし とういち)さん。白衣姿の高橋杜氏の背を追って、歴史ある建物の中を歩きます。
初代・齋藤彌太郎氏が創業した1902年当時の洋館や蔵は、今も11棟すべてが国の登録有形文化財に指定されており、坂に沿って高低差約6メートルにわたり建てられた構造は「のぼり蔵」と呼ばれます。発酵学者・小泉武夫氏が命名したこの名称は、登り窯に似た造りから生まれたそうです。原料処理から搾りまで、工程を上から下へ自然に進める仕組みは、物理的ストレスを減らす構造であり、昔の人々の知恵の結晶でもあります。

『三無い仕込み』という静かな革命。自然に任せる酒づくり
「なしてこんなうめえもんを、わざわざうまくなくすんだろう」
これは、高橋杜氏が齋彌酒造店に入る1984年より、もっと前から抱いていた率直な疑問です。農家に生まれ、祖父の仕込んだ米だけのどぶろくを飲んで育った彼にとって、当時の主流だった炭ろ過や添加物に頼る酒づくりは、どうしても腑に落ちないものでした。そんな折、「いま市場に出回っている酒はおいしいと思えない。お客様に損をさせない味を届けたい」と願っていた齋彌酒造店の4代目・齋藤銑四郎さん(現会長)と出会います。杜氏を探していた齋藤さんは、39歳の高橋さんを迎え、「蔵が倒れない程度なら、思うようにやっていい」と背中を押しました。

こうして高橋杜氏は、加水・炭ろ過・櫂入れ(かいいれ)を行わない「三無い仕込み」を段階的に導入していきます。あるとき、櫂入れをしない酒を、蔵元にさえ事情を知らせずに飲んでもらったところ、「こっちのほうがうまい」と満場一致で評価されたそうです。その後、全国新酒鑑評会での受賞も重なり、試みが正しかったことが証明されました。
蔵元は、現在の5代目・齋藤浩太郎さんに代替わりした今もなお、酒づくりには一切口を出さず、「酒は杜氏を信じ任せる」という姿勢を貫いています。

微生物が主役、ひとは見守るだけ
酒づくりにおいて、高橋杜氏が大切にしているのは「米と向き合い、自然とともにある」ことです。蔵では契約農家や蔵人が育てた米を使い、自社精米。酵母はすべて自家培養し、30年以上かけて選抜したオリジナル株を守り続けています。
全国的に多くの酒蔵が醸造協会から既存の酵母を購入して使用するなか、自社培養にこだわるのは、自分たちの酒に対する強い信念と、他にはない個性や品質への自信のあらわれです。
毎年の米の状態は異なるため、田んぼの稲や精米の状況、米の水分量を見ながら感覚で調整する職人の感覚を研ぎ澄ますことも必要とされます。

「山内杜氏のふるさと」山とともに育った高橋杜氏の原点
1945年、秋田県の山内村(現在の横手市山内)で、高橋藤一さんは生まれました。この村は、秋田県を代表する杜氏集団「山内杜氏(さんないとうじ)」のふるさととして知られています。山の多い土地で、村の約95%が森林。古くから秋田杉の産地としても有名です。
この地域の男性たちは、夏は林業や農業をして、冬は秋田県内の蔵に入って酒づくりを行うのが、あたりまえの暮らしでした。高橋杜氏の祖父も、父も、冬は酒蔵に住み込みで働く「蔵人(くらびと)」でした。その背中を見て育った高橋杜氏が、自然と同じ道を選んだのは、18歳のとき。昭和38年のことです。それから青森県、秋田県内、と数々の酒蔵で修業し、昭和51年より杜氏になり、齋彌酒造店にたどり着きました。山廃づくりに通じ、平成24年には黄綬褒章を受章しています。

「酒づくりは、決してひとりではできません」と高橋杜氏は語ります。仕込みの時期は、朝から晩まで泊まり込みの作業が続きます。寒さの中で声をかけ合い、助け合いながら、手を動かす日々です。学ぶのは技術だけではありません。「整理整頓や掃除の習慣、仲間との信頼関係。『利き酒にひびくからたばこは吸わない』『人間関係を壊すから賭け事はしない』。そうした暮らしの意識そのものが、酒づくりに通じるんです」と高橋杜氏。それは、祖父や初めて仕えた山内杜氏・照井酉松さんらから教わったこと。いま、その教えを自らが次の世代へと伝えています。

微生物たちの声に耳を澄ませ“見守る”酒づくり
現在の蔵では、乳酸菌を加えない「山廃(やまはい)仕込み※」という伝統的な製法を多くの酒に採用しています。高橋杜氏が入蔵した1980年代、主流だったホルマリン消毒をやめ、水拭きだけの掃除に切り替えたことで蔵に菌が住みつき、やがて自然と発酵力が備わっていきました。一般的な速醸仕込みなら1~2週間で済むところを、酒母が完成するまでには約1か月を要します。使う道具も、へらや桶など木製を多く取り入れ、低温から少しずつ暖気を加えながら、蔵付きの菌の働きをうながしていきます。
2001年には日本で初めてオーガニック認証を受けましたが、審査に多額の費用がかかるため、価格転嫁への懸念から後に返上。高品質な酒を適正価格で届けることを選びました。
※山廃仕込み・・・日本酒をつくる際にベースとなる「酛(もと)」と呼ばれる酒母を育てる方法のひとつ。もともとは「山卸し(やまおろし)」という米をすり潰す重労働をしていたのを、自然の力を生かして省いたことから「山卸し廃止酛=山廃」と呼ばれるようになりました。時間をかけて酵母を育てるため、コクがあり、酸味や旨みがしっかりと感じられる日本酒になります。


2018年、NHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』の取材が始まったとき、高橋杜氏は「酒づくりを知りたければ、田んぼにおいで」と伝えたといいます。自然と向き合い、田畑と蔵を行き来しながら、微生物の声に耳を澄ませて生まれるのが『雪の茅舎』です。
東京の日本料理店をはじめ、全国に広まり、IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)や全国新酒鑑評会でも高く評価されています。どれほど知られるようになっても、根底にあるのは「自然とともにある酒づくり」という信念。日本酒の消費量が昭和48年(1973年)を境に減り続けるなか、齋彌酒造店は今も変わらず当時と同じ製造量を保っています。
その姿勢が、蔵の力を支えているのです。

Tsugaru Vidro selectedfor 雪の茅舎

津軽びいどろ
氷華 金彩ロックグラスペア緑陽で味わう
「雪の茅舎」2種
日本酒の味わいは、器によって印象が大きく変わります。口にあたる厚みや角度といった形状だけでなく、色や質感から受ける印象が、気分や感じ方に影響するからです。たとえば、好きなピンクの器なら心がはずみ、金色の盃に注げば特別な気分で味わえるでしょう。

「津軽びいどろ」の酒器といえば、四季をイメージした鮮やかな色合いが特長です。
今回は、高橋杜氏に「この器でうちのお酒を飲んでほしい」という視点で、特にお気に入りのびいどろを選んでいただきました。そこに注がれるのは、『雪の茅舎 純米吟醸』と『雪の茅舎 秘伝山廃』です。

友美 「酒器を選んだポイントはどこですか?」
高橋杜氏 「うちの売上の半分以上を占める定番酒『雪の茅舎 純米吟醸』には黄金色、『秘伝山廃』には緑。ボトルの色に合わせて『津軽びいどろ』の器を選びました」
友美 「今回は、大きめの『氷華 金彩ロックグラスペア緑陽』を選ばれましたね。」
高橋杜氏 「はい。仕込み期間中は、交替で2人ずつが当番となり、私と晩ごはんを共にします。その後、一緒に晩酌もするんです」
友美 「晩酌も、仕事の一部なんですね。器のサイズにも理由があるのでは?」
高橋杜氏 「小さすぎると、一口飲むたびに注ぎ直さなきゃならない。それでは味がつかめません。三口くらい入る大きさがちょうどいいと思って選びました。でも、ちょっと大きかったかな(笑)」
友美 「大は小を兼ねる、ということで(笑)。一応、同じ色のおちょこも用意しました。一般的には、おちょこで飲んでロックグラスは和らぎ水用にしても良いかもしれませんね」

友美 「晩酌では、どのようなお酒を飲まれているのですか?」
高橋杜氏 「県内外の売れ筋のお酒です。まず社長がひと口味を見て、それから蔵人用の冷蔵庫に並べてくれるんです。社長(齋藤浩太郎氏)も「味を語れる人材が蔵を支える」と考え、こうした学びの文化を後押ししています。『雪の茅舎』、それと社長が用意してくれた他の蔵のお酒、さらに前日に飲み切らなかった分の3種類を飲むのがルールです」
友美 「半年間、毎日1本のお酒を買い続けるとなると費用はかさみますが、それを「必須の研修」だと習慣づけている齋藤社長の姿勢に感銘を受けました」
高橋杜氏 「自社のお酒と、他社のお酒を飲み比べ、味覚と感性を磨くことはつくり手として重要です。そうした考えを社長が理解してくれているので、ほんとうにありがたい環境ですよ」
友美 「利き酒はひとりだと限界があるけれど、杜氏や仲間と一緒に飲みながら、その場で感じたことを言葉にして学べるのは、若い蔵人にとって何よりの勉強になりますね」

山が教えてくれた、手を入れすぎない哲学
友美 「定番の純米吟醸は、うま味がありながらも軽やかですね。山廃仕込みのお酒も、酸がやわらかくて食事によく合います。山廃を取り入れている理由は何ですか?」
高橋杜氏 「わたしが蔵に入った1980年代は、山廃はほとんど姿を消していて、続けていたのは隣の飛良泉本舗さんくらいでした。日本酒づくりは伝統産業の最たるもの。大切な技術を絶やしてはいけないと思ったんです」
友美 「最近は若い杜氏が“山廃や生酛の復刻”をうたうこともありますが……」
高橋杜氏 「一度失われた技術は、元には戻せません。ただ酸っぱいだけの酒や、教科書だけで造ったような、芯のない味も多くて。だからこそ、うちの蔵人たちに本物を伝えていく責任を感じています」

友美 「『三無い仕込み』について伺います。櫂入れ(かいいれ)は、いまも日本酒づくりに欠かせない工程とされていますよね。それを“やらない”という大きな決断は、どうしてできたのでしょうか?」
高橋杜氏 「それは、田んぼと山から教わったんです。夏場は山内村に帰り、農作業の合間に、山の間伐や管理もします。崖が崩れると、最初に生える草や、次に育つ木には順番がある。自然のしくみは、ちゃんと秩序をもっているんですよ。そうした姿を見ているうちに、人が手を入れすぎるのは、かえって良くないのではないかと考えるようになりました。酒づくりも同じです。むやみに消毒したり、櫂でかき混ぜたりしない。自然の力を信じて、発酵に任せるべきだという結論に至ったんです」
友美 「山や田んぼの生態系から、酒づくりの本質を見出されたんですね」

友美 「麹米には、兵庫県特A地区産の山田錦を、掛米には秋田酒こまちを使っていらっしゃるそうですね」
高橋杜氏 「はい。少量ですが山田穂も使っています。麹米としては、いまも山田錦がいちばん。ただ環境が変わってきて、秋田県が開発した百田や一穂積も良く、今後は酒こまちからの切り替えもあるかもしれません」
友美 「他の秋田県内の蔵からも、百田や一穂積は評判が高いですね」
高橋杜氏 「百田は山田錦ほどの幅は出ませんが、なめらかで山廃純米に合います。将来が楽しみです。私は今年で杜氏歴49年。50年をひと区切りと考えていますが、酒米の移り変わりを体感してきました。近ごろ若い造り手が古代米を使うこともありますが、正直あまり良い米ではない。話題にはなってもリピートされない。味がともなわなければ、日本酒の未来はない。今の技術で、最も良い味を出せる米を選ぶことが大切です」
友美 「古い米にロマンを感じる気持ちもわかりますが、話題先行で終わるなら、メディアの取り上げ方も考えないといけませんね」
2025年現在、酒米価格の高騰に加え、アメリカへの輸出にかかる関税も重くのしかかっています。「この厳しい局面を越えないと、蔵に未来はありません。次の世代へ、きちんとバトンを渡したい」そう語る高橋杜氏のまなざしには、これまでの歩みによる自負と、齋彌酒造店としての覚悟が宿っていました。

蔵の向かいには、齋彌酒造店が運営する「発酵小路 田屋(たや)」があります。ショップやカフェ、ギャラリー、発酵工房がそろい、どなたでも気軽に立ち寄れます。由利本荘を訪れた際は、ぜひ足を運んでみてください。
ギャラリー
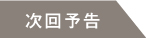
- 次回の「びいどろと巡る、みちのく酒語り 秋田編」は、9月更新予定です。
秋田県五城目町で『一白水成』を醸す福禄寿酒造さんを訪ねます。古くから続く朝市でにぎわうこの町で、地元の米と水にこだわりながら、ドライで洗練された酒造りを続ける蔵元です。
[ sake writer ]

関 友美 せき ともみ
日本酒ライター/ジャーナリスト/唎酒師/日本酒学講師/日本酒品質鑑定士/あおもりの地酒アンバサダー(第一期)/発酵食品ソムリエ/シードルマスター
北海道札幌市生まれ。
酒と地域の物語を丁寧にすくいあげる日本酒ジャーナリストとして、国内外の蔵を訪ね、雑誌、業界専門誌など多彩な媒体で執筆。専門家としてBS-TBS『関口宏のこの先どうなる?!』、TBS『ニューかまー』、朝日放送テレビ『LIFE〜夢のカタチ〜』など、テレビにも出演。近年は、全国の自治体と連携した日本酒観光や商品開発支援、酒蔵のコンサルティングなども手がける。審査員としても複数の日本酒コンクールに参加。酒を通じた地方創生の一助となる活動に力を注いでいる。
- ホームページ https://tomomiseki.wixsite.com/only
- Instagram @tomomi0119seki