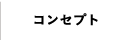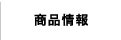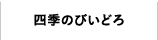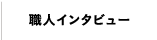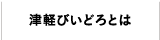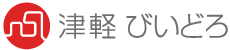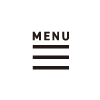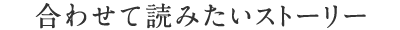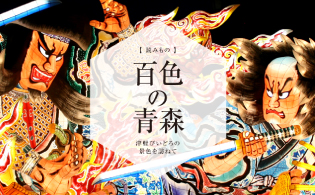「大いに寒い」。字を見ただけで、あぁなるほど…と実感とともに理解できる「大寒」。寒さが厳しさを増して、1年で最も寒くなる時期だとされています。現代の暦でいうと、1月20日頃。小寒から立春まで、30日間の“寒の内”の真ん中にくるのが大寒で、春の兆しが見えるまでの耐えどころともいえます。ただ、この時期の寒さは厳しい反面、食卓に恵みをもたらしてくれる大切なものという一面も。たとえば魚の干物や寒天、凍り豆腐のような寒晒しのほか、日本酒や味噌醤油などでは「寒仕込み」という言葉を目にするように、発酵食品は冬に仕込んだものが最も美味しく仕上がるのです。
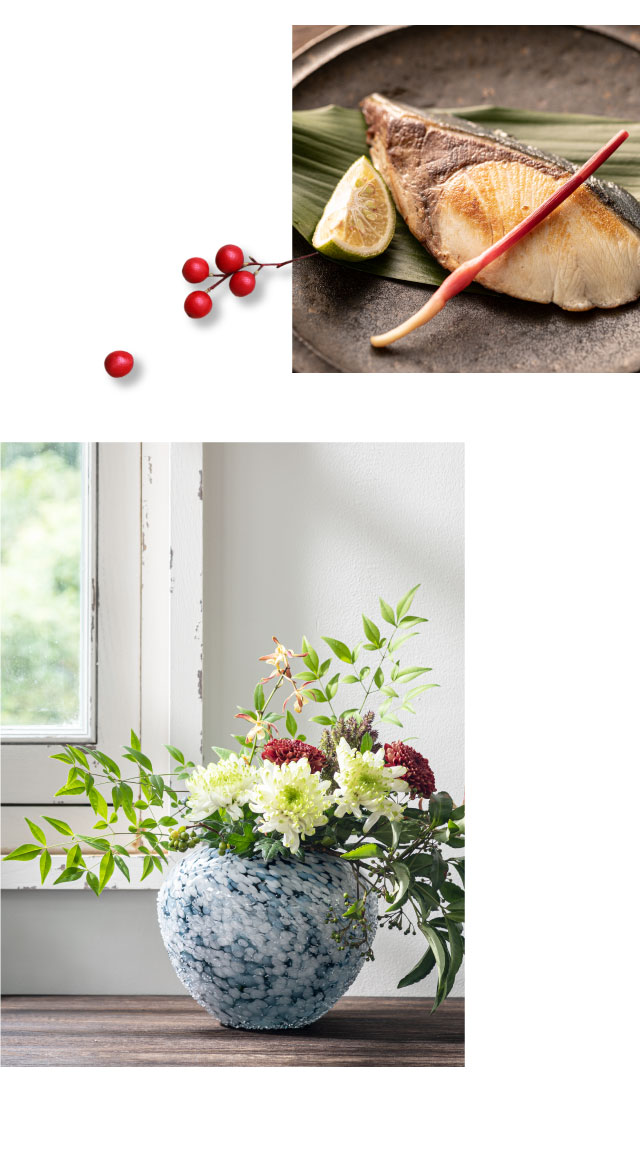


その秘密は寒の内に汲み上げた「寒の水」で、雑菌が少なく体にも良いと、昔ながらの知恵として重宝されてきました。寒の水は江戸時代には“最高の日本酒造り”に欠かせないといわれるほどで、四季を通じて温度管理ができる現代でも、酒蔵では寒仕込み(寒造り)の伝統が受け継がれています。また、低温下では発酵がゆっくりと進むため、日本酒や味噌のような発酵食品は時間をかけて旨みを引き出せるのだとか。寒さを耐えるだけでなく、上手に生かす。日本人のしなやかな気質を感じます。 寒仕込みが仕上がるのは、秋から翌冬にかけて。年が明けてひと息つく大寒の頃には、ひとつ前の冬に熟成された味わいを、あたたかい家でゆっくりと愉しみませんか。