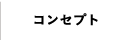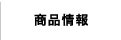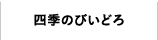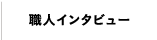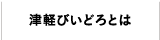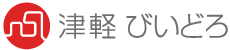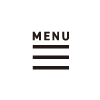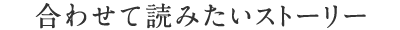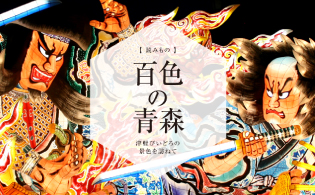【読みもの】びいどろと巡る、みちのく酒語り 秋田編みちのくの風土を地酒から感じる酒器旅

第2回福禄寿酒造 株式会社
-
秋田県南秋田郡五城目町下タ町48

各地で祭りがにぎわう9月の秋田。日中は残暑が厳しくとも、朝晩の空気には秋の気配が漂いはじめます。そんな風景のなかで、土地に根ざし酒を醸す人たちには、その場所でしか語れない物語があります。本連載では、日本酒ライター・関友美が、『津軽びいどろ』とともに各地の蔵を巡り、酒の背景と魅力をたどります。
これまで青森県の12蔵を訪ねてきましたが、今回はお隣・秋田県へ。第2回は五城目町で『一白水成』を醸す『福禄寿酒造』を訪ねました。

山と職人が息づく、
秋田県五城目町
秋田市の北、山あいにある五城目町(ごじょうめまち)は、人口約7,400人の小さな町。林業と木工で栄えた「木の町」で、今も家具や刃物の職人技が息づいています。寒暖差の大きい気候と豊富な雪解け水に恵まれ、農業や発酵文化にも適した風土です。町名の由来は、藤原李盛の居城「五城目城」とされ、500年以上続く朝市にも歴史の深さがにじみます。地域資源を生かした挑戦が進み、若い移住者も増えつつあります。

赤レンガの蔵が紡ぐ
三百年の物語
五城目の朝市通りに、元禄元年(1688年)創業の酒蔵「福禄寿酒造」はあります。町の玄関口に佇むこの蔵は、上酒蔵・下酒蔵、応接間、住宅を含む4棟が、平成8年に国の登録有形文化財に指定されました。赤レンガの壁と風格ある看板は、町の風景に溶け込み、訪れる人の足を自然と止めます。
「ようこそ」と穏やかな笑顔で迎えてくれたのは、16代目蔵元であり代表取締役社長の渡邉康衛(わたなべ こうえい)さん。酒蔵のはじまりは、石川県から移り住んだ渡邉家の祖先が、どぶろく造りを始めたことにあります。江戸時代末期からは清酒造りに移行し、以来300年あまり、地元の水と米に寄り添いながら、五城目の風土に根ざした酒を醸し続けています。

16代目・渡邉康衛が挑んだ、
蔵の再生と革新
酒蔵の伝統を次の世代につなぐ存在が、16代目の渡邉康衛さんです。1979年生まれで、2001年に東京農業大学醸造学科を卒業後、家業である酒蔵に入りました。「親父が社長で、会社も大変な時期だったから、すぐ帰ってこいと言われて」と当時を振り返ります。入社当時は、現在の倍近い量の酒を造っていましたが、その多くは安価な価格の普通酒。さらにビールメーカーの二次問屋も兼ねていたため、日本酒の仕込みに加え、ビールの配達にも奔走する日々が続きました。
「この経営状態をなんとか変えたい」と一念発起し、酒造りに力を注ぐ中、思いがけない出会いにも助けられ、2006年、27歳の時に新たなブランド「一白水成(いっぱくすいせい)」を立ち上げました。

“一白水成”誕生、
その裏にあった出会い
長年「福禄寿」の名で親しまれてきた福禄寿酒造は、時代の流れとともに普通酒が主流となっていました。そんな中、蔵に戻った渡邉康衛さんは、蔵人で現在は杜氏(とうじ:酒造りの責任者)を務める一関仁さんとともに、品質向上をめざして試行錯誤を重ねていきます。
あるとき、秋田県酒造組合の勉強会で、全国の地酒専門店やデザイナーが酒を評価する場に参加。東京・聖蹟桜ヶ丘「小山商店」の小山喜八さんと出会いました。現状を伝えると「一度うちに来なさい」と誘われ、店舗を訪れます。そこに広がる光景に、渡邉さんは息をのみました。棚いっぱいに全国の日本酒が並び、客が次々に訪れては真剣な表情で酒を選び、丁寧に説明する店員の言葉に耳を傾けながら、一本ずつ買い求めていく――。「日本酒がこんなふうに売れていくなんて」と、まるで夢のような光景に驚いたといいます。

「一升瓶で三千円以内、いい酒をつくってごらん」と背中を押され、美山錦を50%まで精米した純米吟醸を仕込み、小山商店に送りました。すると「いいね、五ケースちょうだい」と即注文。その後も継続して発注が入り、取引が始まりました。
この酒は、渡邉さんと一関仁さんが、深夜の麹室で理想を語り合いながら、少しずつ技術を高めていった成果でもあります。一関さんは、渡邉さんが蔵に戻る前から、前任の山内杜氏のもとで酒造りに携わってきた造り手。そのときに培った知識や経験も、いまの酒造りにしっかりと活かされています。山内杜氏組合に所属する社員杜氏でもあり、寡黙で実直な職人肌の人物です。

こうして2006年、新たなブランド「一白水成(いっぱくすいせい)」が誕生。「白い米と水から成る、一番うまい酒にしたい」という想いが名前に込められました。華やかさとほどよい酸味、キレのある味わいは、徐々に多くのファンをひきつけていきます。
仕込みは、一関さん、渡邉さん、そして弟の良衛さんを含む3人で担っていました。しかし2008年、良衛さんが仕込み中にタンクへ転落し、24歳の若さで命を落とすという痛ましい事故が起こります。「しばらく酒造りに向き合えませんでした。でも“事故のせいで酒が悪くなった”とは言われたくなかった。だからこそ、これまで以上にいい酒をつくろうと決めました」
こうして挑んだ「一白水成」は、銘柄を伏せて審査される「仙台日本酒サミット」で全国の酒蔵や酒販店から高く評価され、一位を受賞。3年連続で一位を獲得し、一躍全国に名を広げました。
弟のため、仲間のため、そして飲み手のために――。「この地でしか造れない、一番うまい酒を」。渡邉さんの挑戦は、今も続いています。
酒米も水も人も、
五城目と育てる「一白水成」
「5月、森山から見下ろす田んぼと夕日――この絶景こそが、酒造りの原動力なんです」
標高325メートルの森山からは、五城目町をはじめ、男鹿半島や日本海まで見渡せると渡邉さんは語ります。
2015年、地元農家10軒と「五城目町酒米研究会」を発足。「美山錦」など4種の酒米を栽培し、今では原料米の約9割を地元でまかないます。田植えから収穫までの半年、農家・試験場・役場と田の状態を見て回る「現地調査」も実施。緊張しながらも「私の田んぼです」と誇れる関係が、良い米を育ててくれるといいます。最良の米は「一白水成プレミアム」に使用されています。

蔵の地下から湧き出すのは、マグネシウムを豊富に含む中硬水です。ミネラル分が多い水は発酵が進みやすく、当時主流だった、舌触りが柔らかく甘みのある酒造りには不向きでした。そのため、かつては軟水を外から運び入れたり、水道水を試したこともあります。
しかし、「初代はこの水を求めて蔵を構えた」という原点に立ち返り、この水にふさわしい酒を醸し、この水と共に歩むことを決意しました。
2024年、町内6社で「発酵パーク株式会社」を設立しました。福禄寿酒造を中心にした酒蔵ツアーの企画・運営のほか、視察研修や教育留学の滞在受け入れ、朝市出店者の定着をめざした宿泊施設の整備など、地域全体で多彩な取り組みが進んでいます。
代表の渡邉さんは「町とともに生きたい」と語り、SNSでも地元の祭りや野球、田んぼの様子など、地域へのまなざしがあふれています。五城目の力を背に、福禄寿の酒は今日も醸されています。

NEXT5とともに築いた
秋田酒の地図
「NEXT5」は、2010年に秋田の若手蔵元5人が結成した酒造りユニットです。きっかけは、「ゆきの美人」の小林忠彦さんが、広島の蔵元集団「魂志会(こんしかい)」の記事を雑誌で見て、「秋田でもこんなことができたら」と声をかけたことでした。
集まったのは、「白瀑(しらたき)」の山本友文さん、「新政(あらまさ)」の佐藤祐輔さん、「春霞(はるかすみ)」の栗林直章さん、そして「一白水成」の渡邉康衛さん。いずれも自ら現場で仕込みを担う蔵元たちです。
技術交流から始まった活動は、やがて共同醸造や発表イベントへと発展し、2014年以降は、村上隆さんやパティシエのピエール・エルメさんら各界のクリエイターとのコラボレーションも実現しました。震災後、東北の酒に注目が集まる中、NEXT5は「秋田の酒が面白い」と言われる時代の先駆けとなったのです。
少し年上の兄貴分として、山本さんや佐藤さんを支え導いたのが小林さんです。秋田における蔵元杜氏の先駆者であり、NEXT5を立ち上げた立役者として、酒造りの姿勢や在り方を最初から示してきました。その背中を追うように、山本さんと佐藤さんが勢いよく牽引し、栗林さんは数字や全体の資金管理を支えました。渡邉さんは記録や議事をまとめ、時に意見の異なるメンバーの間を取り持つなど、グループを安定させる要の役割を担ってきました。造る酒の個性も異なり、蔵元それぞれのキャラクターや性格もまったく違います。だからこそ遠慮なく指摘し合い、高め合うことができた。互いの違いが結束を強め、唯一無二のチームを築き上げていったのです。

カフェ“HIKOBE”に宿る
蔵の精神
福禄寿酒造では、米づくりから酒造りまで、地元と歩む姿勢が蔵全体に息づいています。その象徴が、2018年に蔵の斜め向かいに開設された「下タ町醸し室 HIKOBE(ひこべ)」です。元たんす屋を改装した木の温もりある空間で、カフェ兼直売所として仕込み水のコーヒーや酒粕スイーツ、日本酒の飲み比べ、オリジナルグッズが楽しめます。
とくに印象的だったのが、「一白水成」と大きく記された米袋をリメイクしたトートバッグです。本来、農家が玄米を精米所に運ぶ袋に名前を印字する必要はありませんが、「自分たちの米が一白水成になる」という誇りを持ってほしいという渡邉さんの想いが込められています。一枚の袋にも、酒造りを支えるチームの心が息づいていると感じました。そんな一品を、わたしたちは日常に迎えることができるのです。


Tsugaru Vidro selectedfor 一白水成

津軽びいどろ
「酒器 岩清水酒器セット」
で味わう
「一白水成」2種
日本酒の味わいは、器によって印象が大きく変わります。口にあたる厚みや角度といった形状だけでなく、色や質感から受ける印象が、気分や感じ方に影響するからです。たとえば、好きなピンクの器なら心がはずみ、金色の盃に注げば特別な気分で味わえるでしょう。

「津軽びいどろ」の酒器といえば、四季をイメージした鮮やかな色合いが特長です。
今回は、渡邉さんに「この器でうちのお酒を飲んでほしい」という視点で、特にお気に入りのびいどろを選んでいただきました。そこに注がれるのは、『一白水成 純米吟醸』と『一白水成 Premium(プレミアム)』です。
一白水成のテーマカラーは「青」
友美 「酒器を選んだポイントはどこですか?」
渡邉さん 「コーポレートカラーである青の酒器を選びました。きれいな青ですね」
友美 「“一白水成”の“白”でも良さそうですが、なぜ青なんでしょう?」
渡邉さん 「NEXT5を結成した際に、各蔵でテーマカラーを決めたんです。新政は緑、ゆきの美人は白、山本が赤、春霞はピンク。そして一白水成は、定番の純米吟醸ラベルが濃い青だったので、うちは青に。今では僕やスタッフがかぶる帽子や、ボトルキャップのロゴにもこの青を使っています」

渡邉さん 「このお酒がその純米吟醸です」
友美 「たしかに、一白水成といえばコレ!という気がします。仕込み水由来のミネラル感と旨味が一体となり口の中ですがすがしい味わいとなり、酸も感じ、最後はドライ」
渡邉さん 「もうひとつは『一白水成 Premium』。その年もっとも良質な美郷錦を育てた一軒の農家の米を使い、45%まで丁寧に磨いた純米大吟醸です」
友美 「シルキーな舌触りと繊細な米の旨み、洗練されたキレと淡い余韻が心地よく広がります。箱やラベルに農家の名前を毎年印刷していると聞き、その丁寧さと愛に驚きました。米づくりへの敬意と、誇りを共有したいという思いが伝わってきます。」

節目のその先へ──仲間と歩んだ10余年と酒の未来を語る
友美 「参加されていた日本酒醸造グループ『NEXT5』は、2024年2月に活動を休止されましたね」
渡邉さん 「14年続けて、やりきったという実感があります。もともとは技術向上を目的に集まった仲間でしたが、やがてイベントや企画など、外からの期待が大きくなってきて。一度、各自の蔵ときちんと向き合おうと、休止を決めました。ただ今でも集まって飲んで、情報交換はしていますよ」
友美 「共同醸造は、販売目的ではなく、あくまでも醸造の見直し。以前『春霞』の栗林酒造店さんを訪ねたとき、いくら掃除していても、他のメンバーから『きったねーな』と厳しい言葉を投げかけられたそうで、迎える当日はかなり緊張していたと伺いました」
渡邉さん 「まさにその通り(笑)。『この作業、何のため?』と聞かれて、『昔からやってるから』と答えると、『じゃあ、やらなくていいんじゃない?』って返ってくる。米一つ運ぶ方法も蔵によって違うから、『こっちの方が良くない?』の連続でした」

友美 「そこまで本音で言い合える関係って、蔵にとっても人生にとっても貴重ですよね」
渡邉さん 「ほんとに。おかげで全工程を見直すことができ、本当に勉強になりました」
友美 「秋田には技術力の高い山内杜氏(さんないとうじ)の文化が根づいていて、雪の茅舎や天の戸といった先駆者もいますが、県全体が注目されるようになったのはNEXT5の存在が大きかったと感じます。活動休止は、まさに時代の節目のようでした」
渡邉さん 「『一白水成』を出した2006年ごろ、秋田は“不毛の地”といわれていて、技術はあっても流通面などで苦戦していました。でも今は若い蔵も増えて、これからますます面白い酒が出てくるはずです」
友美 「これからも秋田の酒から目が離せませんね」

友美 「酒蔵の中を見学して、冷蔵設備のない場所で純米大吟醸などの高級酒を仕込み、逆に冷蔵設備のある蔵で日常酒をつくっていることに驚きました。一般的なアイデアとは逆ですよね。なぜそうされているのですか?」
渡邉さん 「晩酌で飲まれるお酒は、より多くのお客様の口に入るので、品質の安定と向上のために冷蔵管理を徹底しています。高級酒ほど、その年の気温や気候といった個性を反映させ、“あの冬は寒かったよね”と、年ごとの記憶を語れるような味わいを目指しているんです」

2025年、製造所の裏手に新たな瓶詰め場が完成しました。これにより、搾りたての酒を詰める圧搾機から瓶詰め場までの距離が大幅に短くなりました。以前は長いホースで酒を送り、その間に空気に触れて酸化する可能性や、振動によるストレスで味わいに影響が出ることもありました。距離の短縮で負担が減り、「今年の一白水成は発泡感がある」と評されるほどの鮮度を保てるようになったのです。充填機も液面非接触型に改め、低温加熱殺菌装置(パストライザー)も導入しました。
ブランド価値向上にも取り組み、キャップをロゴ入りに一新。瓶詰め場の隣には出荷場を併設し、ラベル貼りや箱詰めの動線は、蔵元ひとりではなくスタッフ全員で意見を出し合い、全員が納得し、より良くなる方法を考えながら決めたそうです。
「ありがたいことに、長く勤めてくれる人が多く、いまでは父の代に加わったスタッフと、私の代で新たに迎えたスタッフが、ちょうど半々になりました。」
がむしゃらに駆け抜けた時代を経て、五城目町とともにある酒造りは、さらに深みを増していくでしょう。素朴な暮らしと人のぬくもりが息づく町で、酒は育ちます。五城目の風土と「一白水成」の味わいを、ぜひ現地で感じてみてください。
ギャラリー
酒器
12色のグラス
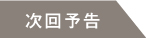
- 次回の「びいどろと巡る、みちのく酒語り 秋田編」は、11月更新予定です。
訪ねたのは、日本海を望む秋田県にかほ市で『飛良泉』を醸す飛良泉本舗さん。1487年(長享元年/室町時代)創業、500年を超える歴史を持つ、国内でも屈指の老舗酒蔵です。今回は、まだ専務という立場ながら、蔵の未来を見据え、自らの手でブランドを再構築しようと奮闘する若き後継者の姿に迫りました。
[ sake writer ]

関 友美 せき ともみ
日本酒ライター/ジャーナリスト/唎酒師/日本酒学講師/日本酒品質鑑定士/あおもりの地酒アンバサダー(第一期)/発酵食品ソムリエ/シードルマスター
北海道札幌市生まれ。
酒と地域の物語を丁寧にすくいあげる日本酒ジャーナリストとして、国内外の蔵を訪ね、雑誌、業界専門誌など多彩な媒体で執筆。専門家としてBS-TBS『関口宏のこの先どうなる?!』、TBS『ニューかまー』、朝日放送テレビ『LIFE〜夢のカタチ〜』など、テレビにも出演。近年は、全国の自治体と連携した日本酒観光や商品開発支援、酒蔵のコンサルティングなども手がける。審査員としても複数の日本酒コンクールに参加。酒を通じた地方創生の一助となる活動に力を注いでいる。
- ホームページ https://tomomiseki.wixsite.com/only
- Instagram @tomomi0119seki