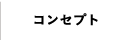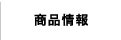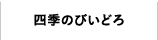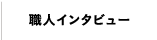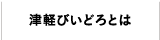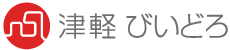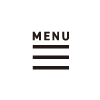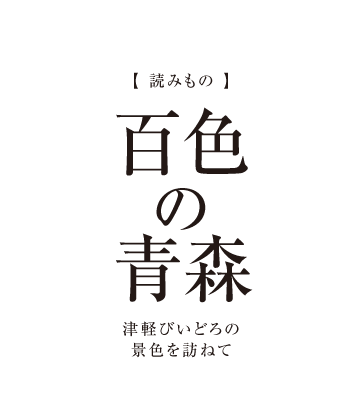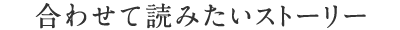『津軽びいどろ』の生まれた青森県の多彩な「いろ」と「ひと」と「もの」、そして「こと」を訪ね取材、土地の魅力を発信していくコンテンツです。今回は、蔵の移転とリブランディングという大きな決断を一身に受け、新しい蔵の核心を託された杜氏・河合貴弘さんの物語を中心に、六花酒造の新しい歩みをご紹介します。
<移転前のお話はこちらから 青い森の日本酒と津軽びいどろ「六花酒造」>
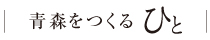


岩木山の麓で、新しい酒が生まれる
津軽平野に広がるりんご畑に囲まれるようにして、雄大な岩木山(いわきさん)の麓に、凜とした空気をまとう酒蔵が見えてきます。かつてここもりんご畑だったという土地に、三百年の歴史を誇る六花(ろっか)酒造は、未来への一歩となる新しい醸造所を構えました。
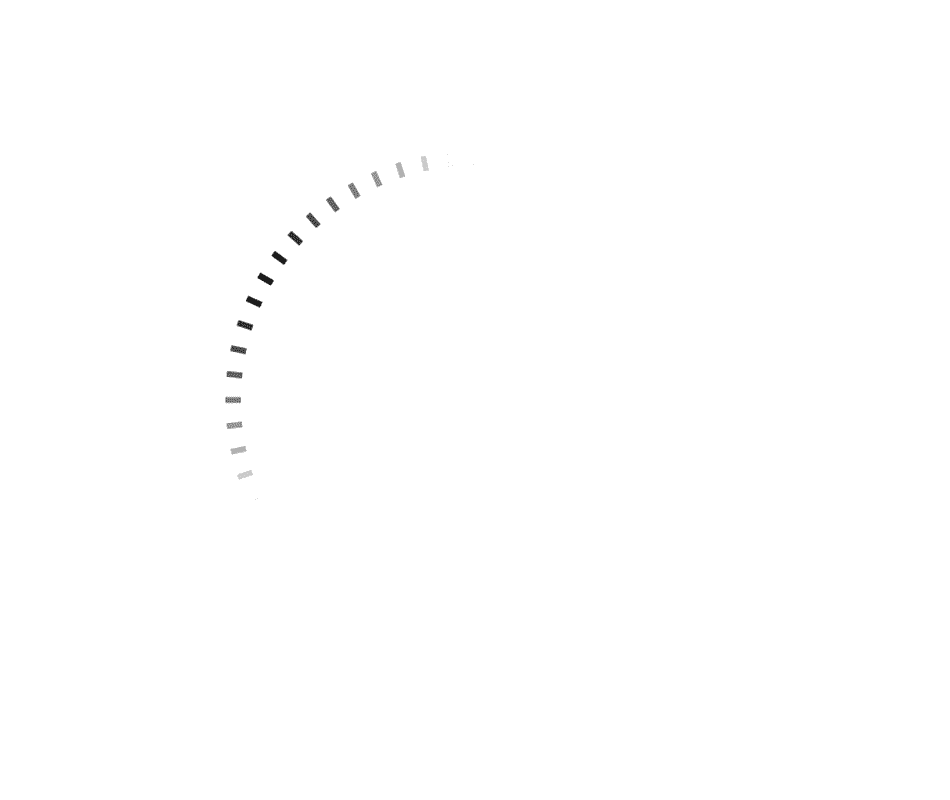
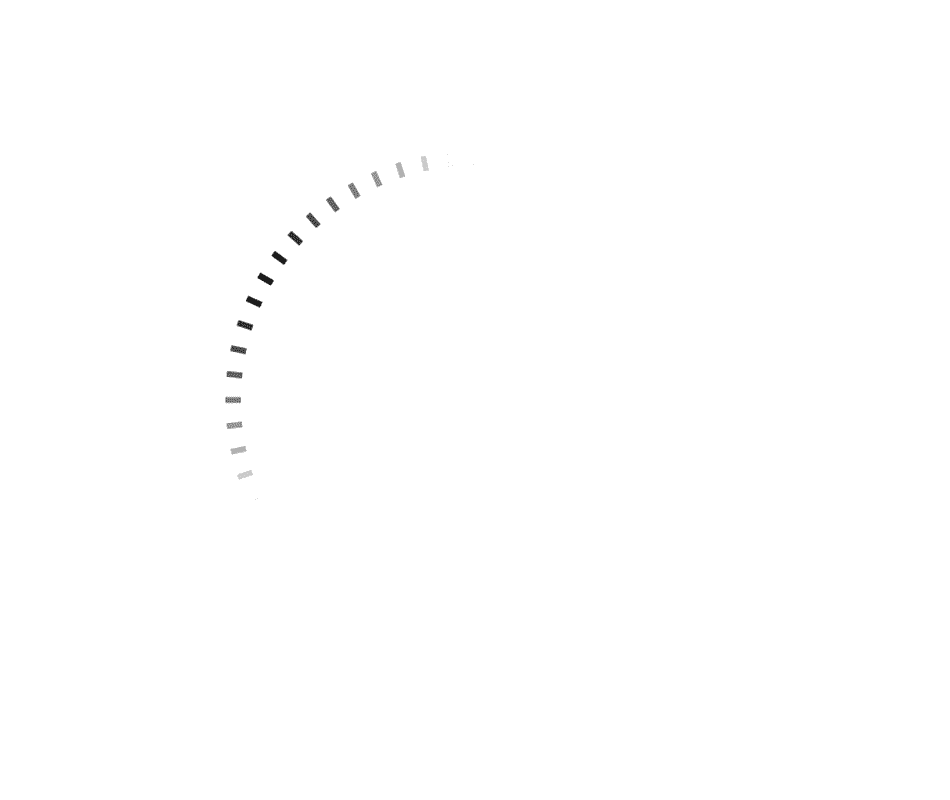
この日、私たちを迎えてくれたのは、社長の北村裕志さんと杜氏の河合貴弘さん。お二人の津軽弁まじりの素朴な話しぶりに耳を傾けるうち、まるで良い地酒に触れたときのようなやすらぎを覚えました。そして、その穏やかな語り口の奥に込められた想いから、この蔵の明るい未来へと続く物語が始まる予感がしました。
三百年の歴史。
巨大な蔵を経て、未来へつなぐ一献
六花酒造の歩みは、東北の酒造史における一つの象徴と言えるかもしれません。もともとは弘前市内でそれぞれに歴史を刻んでいた、「高島屋酒造」「白梅酒造」「川村酒造店」。この三つの酒蔵が大手酒蔵に対抗するために手を取り合い、1972年(昭和47年)、『六花酒造』が誕生しました。その後、田んぼの真ん中に建てられた巨大な蔵は、大量生産の時代を見据えた、まさに高度経済成長期のしるしでした。
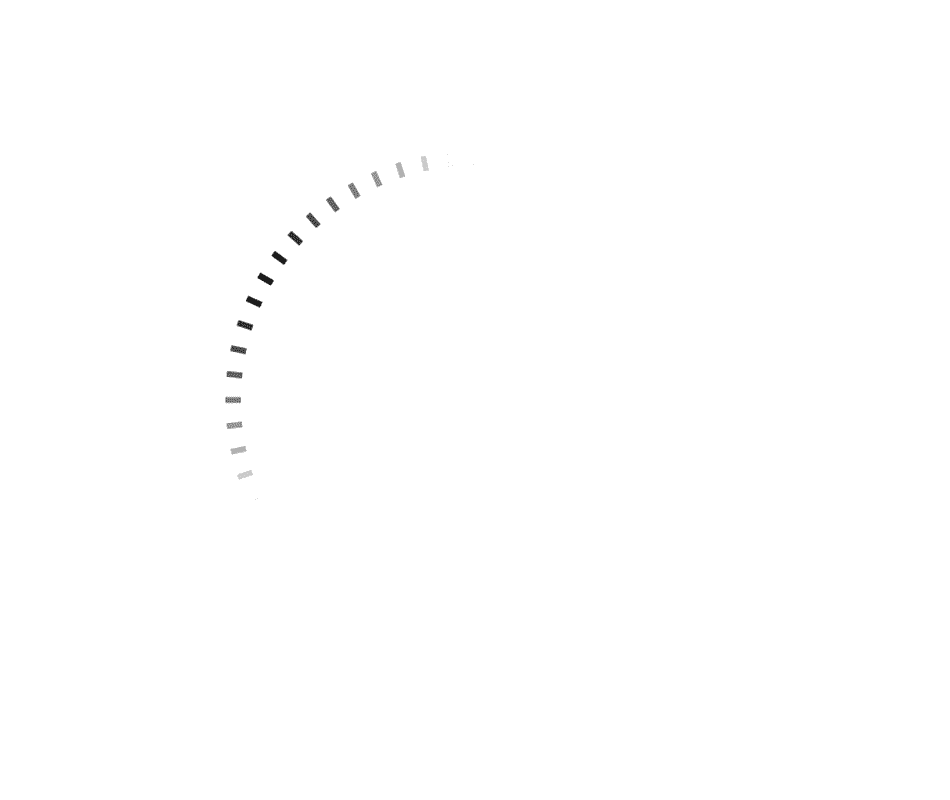
しかし、日本酒の国内消費量は1973年をピークに減少に転じます。やがて日本酒業界が、品質を重視する酒蔵と、価格を追求する酒蔵へと二極化していく中で、巨大な蔵を持つ六花酒造は、必然的に量を造ることが優先され、価格競争の渦中へと巻き込まれていきました。
看板銘柄「じょっぱり」が地元で長く愛され続けた一方で、かつて強みであったはずの巨大な設備は、次第に細やかな酒造りの自由を奪う、重荷のような存在となっていったのです。
そして、1997年に入社し、2006年に杜氏となった河合さんにとって、その規模こそが理想の品質を追求する上での、もどかしさの源になっていきます。
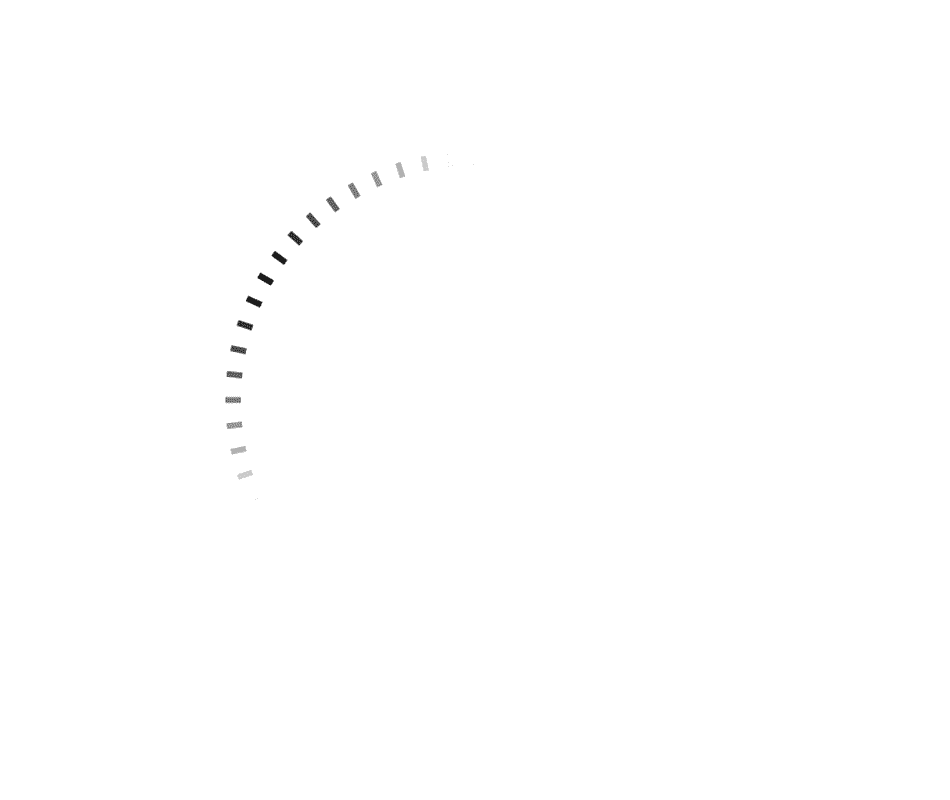
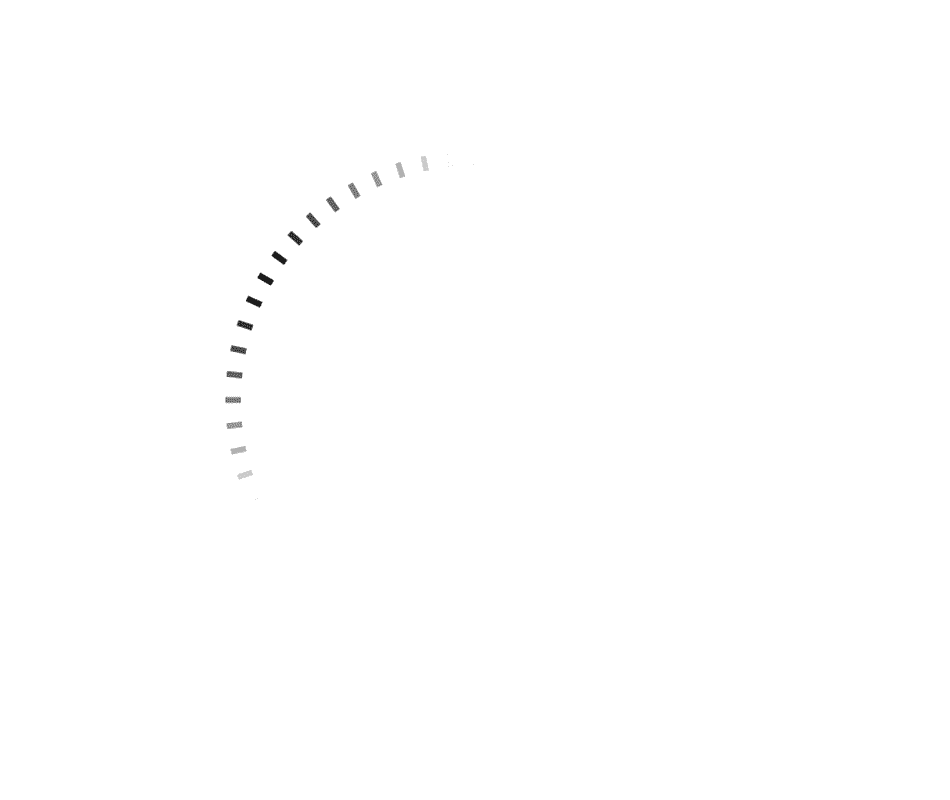
「昔の蔵はとにかく大きくて。醪(※もろみ:お米がアルコール発酵している液体)の段階で良い手応えを感じても、搾り機や瓶詰めまでの動線が長く、最後の搾りで『あれ?変わったな』と。そこが一番残念でした。もちろん管理は徹底していましたが、理想とする品質を最後まで追求しきるには、どうしても物理的な限界があったんです」
そんな彼の情熱の原点と言えるのが、全国新酒鑑評会への挑戦でした。「杜氏になったからには、まずコンテストで認めてもらいたい」。その一心で、以前の巨大な蔵の片隅で、理想の酒を造るための小さな仕込みタンクの購入を社長にお願いしたこともあったといいます。研鑽を重ね、平成25酒造年度(2013BY)にはじめて金賞を受賞。
この快挙は、河合杜氏の情熱と技術が正しかったことの証であり、のちに新しい蔵の設計という未来をその手に引き寄せる、運命の一歩となるのです。
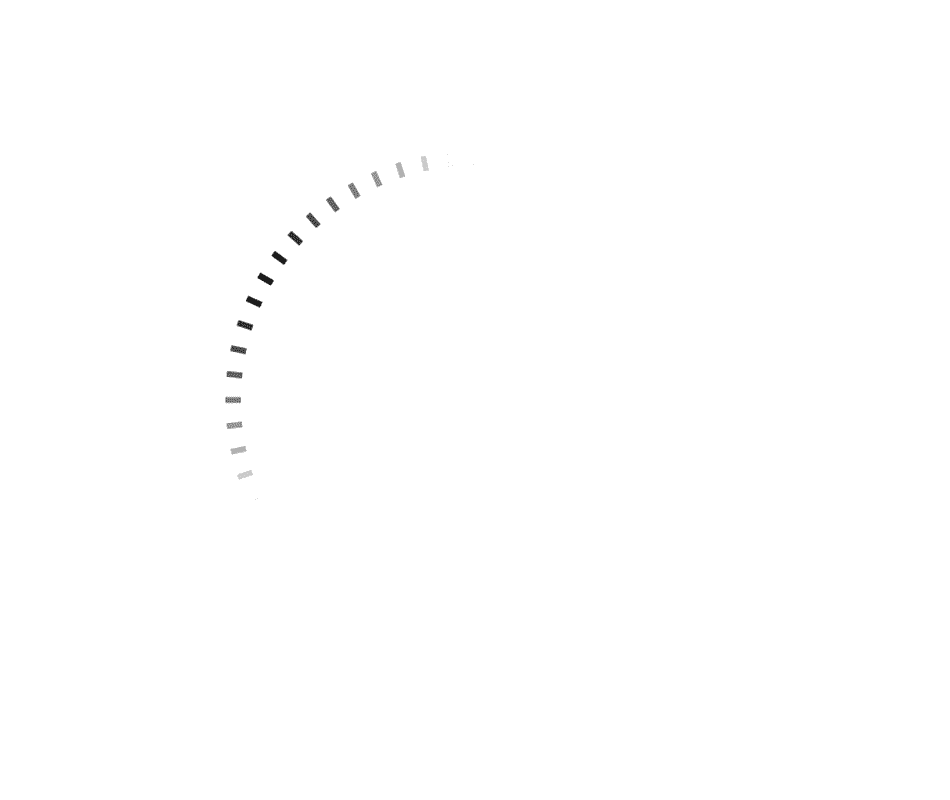
杜氏の夢、岩木山の水と出会うとき
時代の変化とコロナ禍を経て、会社は大きな決断を下します。老朽化した蔵を閉じ、新しい場所で再出発することを決めたのです。製造量が減っていたこともあり、現在の規模に適した蔵を建てる必要がありました。そして、杜氏の河合さんに未来を託したのが、北村社長でした。
「一切口は出さない。君の作りたい酒を、君の思うように造ってくれ」
北村社長は青森市の酒屋の長男として生まれ、修業のために六花酒造の前身である高島屋酒造に入社。営業畑で力を尽くし、やがて抜擢されて社長へと歩んできた、異例の経歴を持つ生え抜きの社長です。だからこそ、その言葉には特別な重みがありました。その大きな信頼を受け、河合さんの挑戦が静かに始まります。
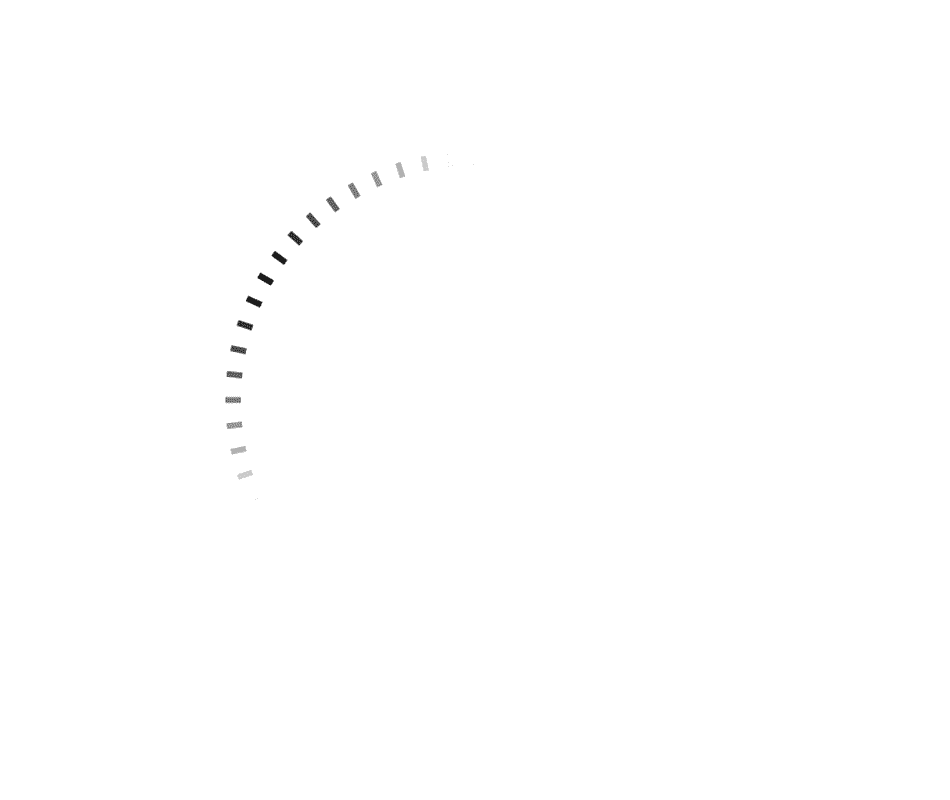
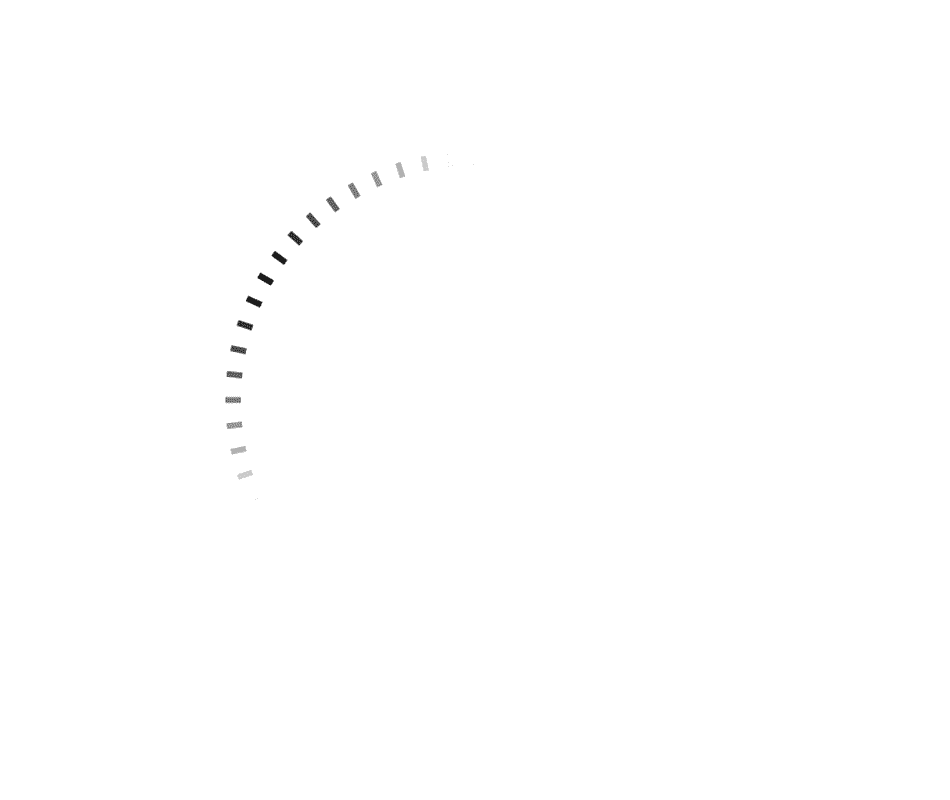
「ここの土地の広さが決まり、建物の大きさも概ね定まったところで、『せば(津軽弁で“それなら”)、造りの面積がどれぐらい取れるか』と。その中でどう機械を配置していくか、一つひとつ決めていきましたね」と河合さん。
一枚の図面を前に、彼はまず、過去の苦労を思い返したといいます。掃除に手間取った経験から、床は水はけの良い素材に。蔵人たちの動きを考え、無駄のない動線に。そして、今後は一年を通して酒づくりすることを考えて、休ませることが必要な木の麹室ではなく、手入れの行き届くステンレス製に変更しました。
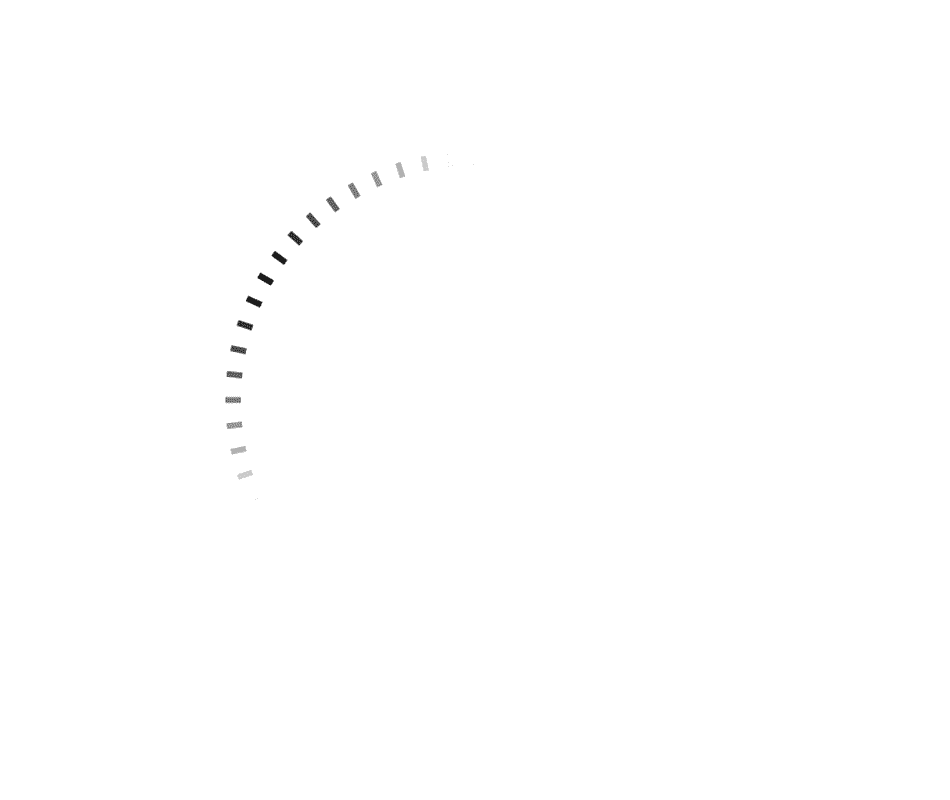
移転先の候補は市外の廃校など様々ありましたが、最終的に選んだのは岩木山の麓でした。「どうしても弘前の酒蔵でいたい」。その想いが、酒造りで最も重要な「水」という宝物をもたらします。
「前の蔵の水は少し硬めで辛口向きでしたが、ここでは岩木山が濾過してくれた、柔らかな伏流水が使えるようになりました。これが、私たちの目指す酒質にぴったりだったんです」。
霊山・岩木山が抱く、静かな雫。
雪解けの永い旅が磨き上げた
透明な恵み。
それは「杜來」となり
津軽の地に射す、希望となる。
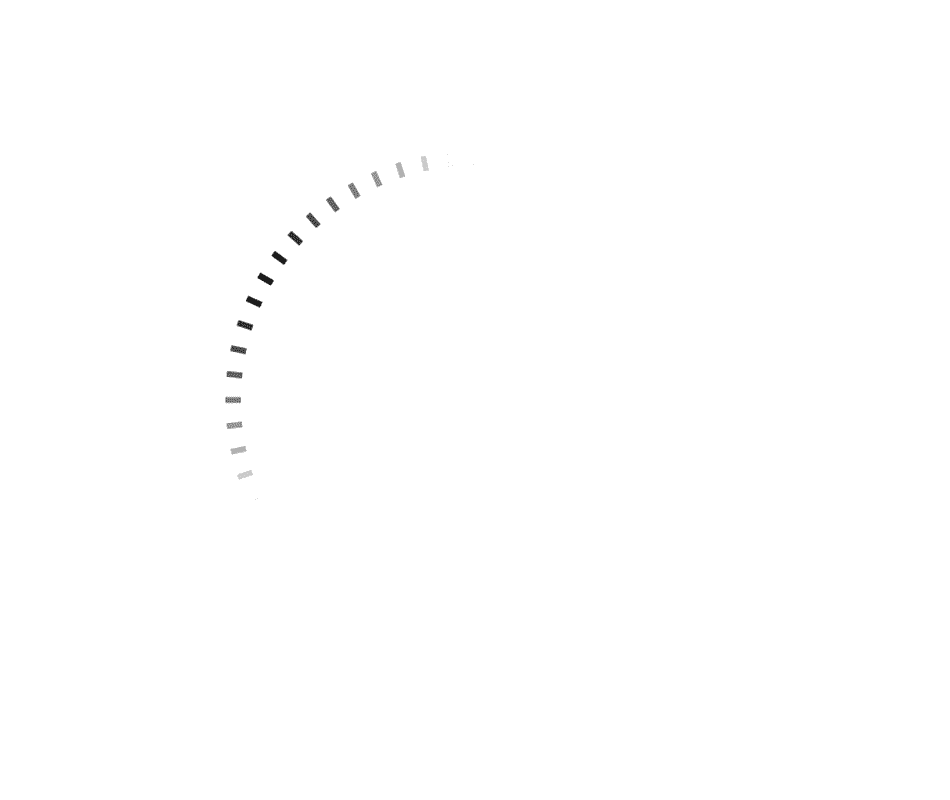
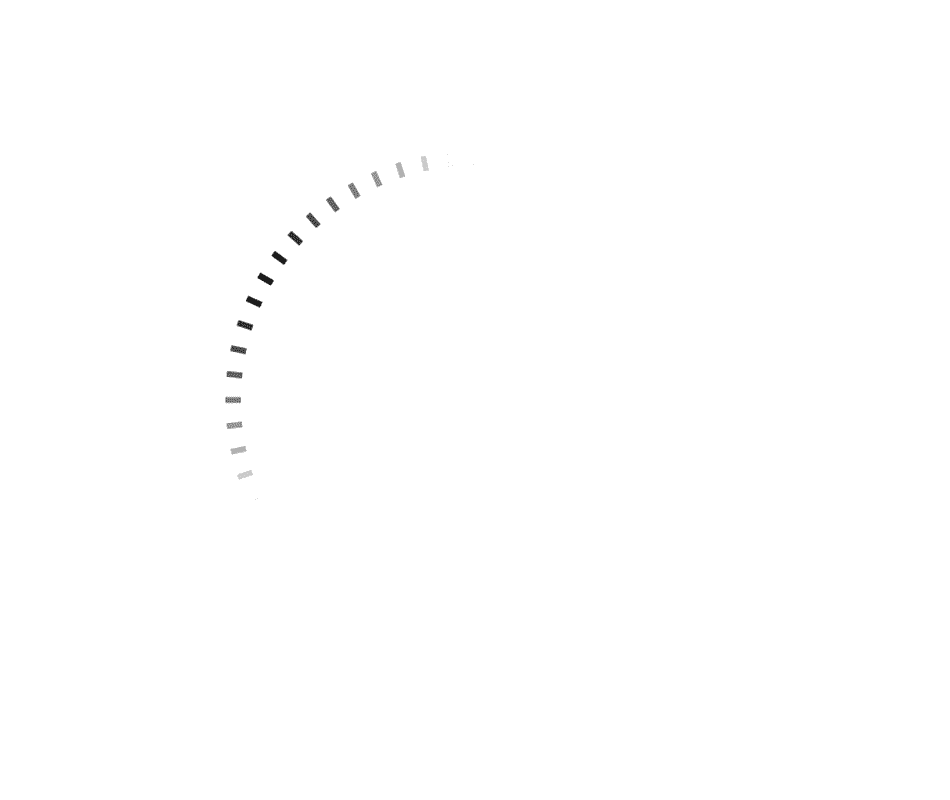
すべてを見せる、心からのおもてなし。
杜氏を筆頭に、みんなで歩みを進める
新しい蔵は、河合さんのこだわりが隅々にまで息づいています。ワンフロアで完結するコンパクトな設計。甑(こしき ※米を蒸す道具)も、旧蔵で小仕込みに使っていた愛着のある道具を受け継ぎました。
そして、最も大きな変化の一つが「搾り」の工程です。かつて癖に悩まされた自動圧搾機から、伝統的な「槽(ふね)」という、酒袋を重ねて優しく搾る方式へ。お酒に余計な負荷をかけず、澄んだ味わいを引き出すためです。
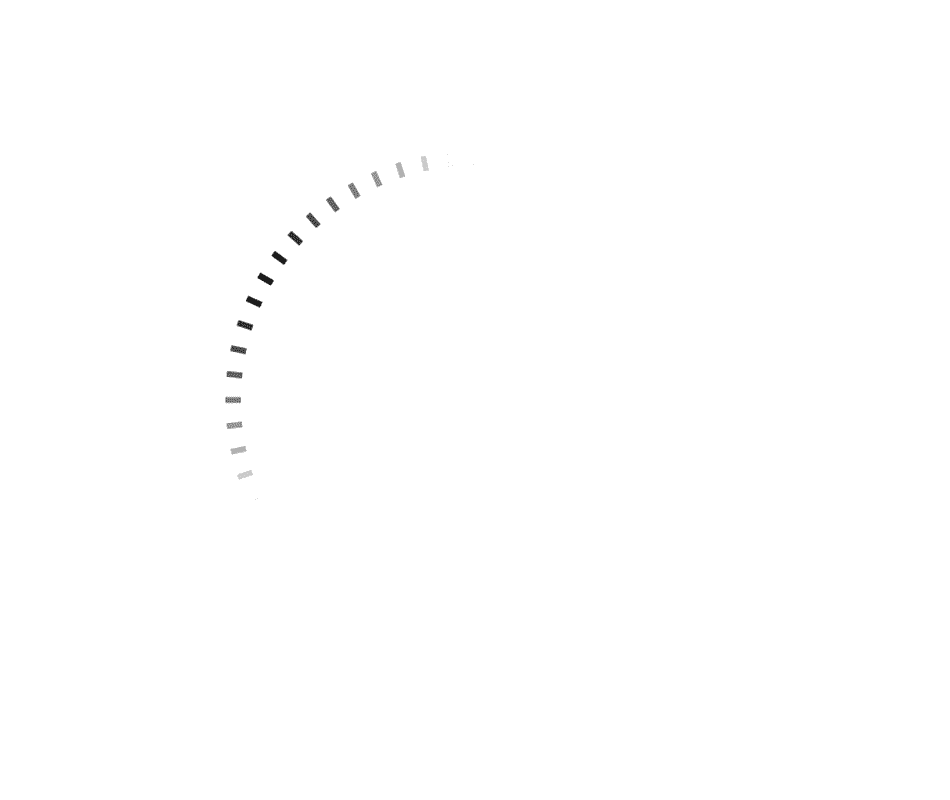
こうして新しい蔵の象徴として誕生した、新ブランド『杜來(とらい)』。
その名前は、全社員からの公募で決まりました。込められた願いは二つあります。一つは「三百年の歴史と、杜氏の技術や想いを、輝かしい未来へ繋いでいきたい」という想い。そしてもう一つは、その志を英語の「TRY」に重ね、「常に挑戦し続ける」という決意です。蔵人みんなの願いが込められています。そのラベルの柔らかな書体は、車で10分弱の距離にある『岩木山神社』で使われている文字を参考にさせてもらったもの。この土地への敬意が、そこにも静かに込められていました。
また、イラストにも物語があります。描かれているのは、岩木山に棲む野生の仲間たち。野ウサギやカモシカ、サンショウウオ、イヌワシ、山猿、クマゲラ——絶滅危惧種や天然記念物も含まれるこれらの生きものに、この地の自然と共に未来を紡ぎたいという願いが託されています。
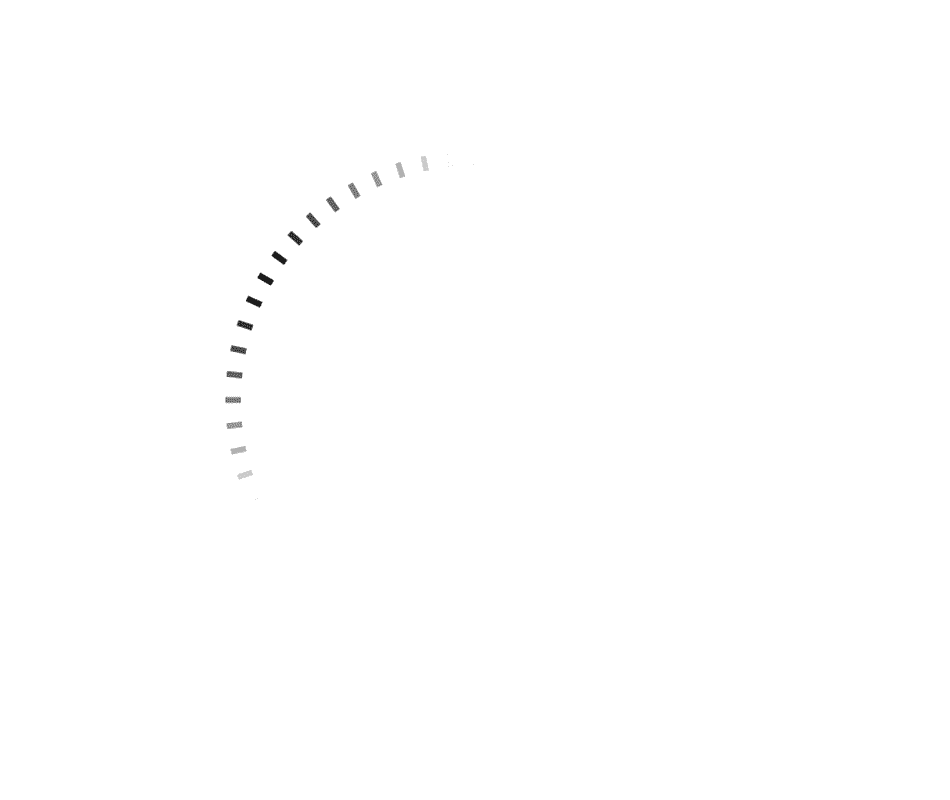
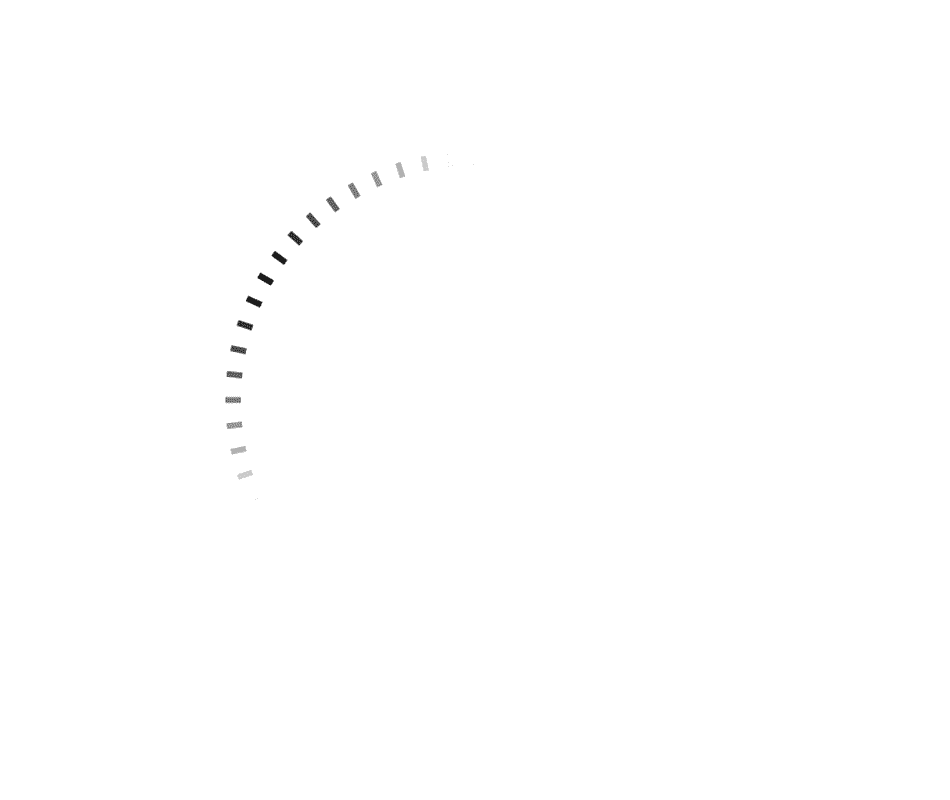
「まず、誰が飲んでも『美味しいね』と言っていただけるお酒を。その中でこれからは、この蔵ならではの『個性』も探していきたいんです」。
その言葉を裏付けるように、蔵の売店にはモニターが設置されています。麹室や仕込みタンクなど、蔵の心臓部に置かれたカメラの映像が、そこには映し出されていました。かつての酒蔵では考えられなかった、すべてを公開するその潔さは、まさに彼らの酒造りへの揺るぎない自信と、訪れる人への誠実な「おもてなし」の覚悟の表れなのでしょう。
さらなる個性を模索しながら、
美酒「杜來」は、未来へと紡いでいく
酒蔵の売店には、無料試飲コーナーが並びます。蔵の直売所で、完成したばかりの『杜來』を一口いただきました。穏やかな香りと、すっと喉に染み渡る清らかな味わい。それでいて、インパクトのある旨味が広がり、河合杜氏の酒づくりへのこだわりが垣間見えます。その一滴に、彼らが乗り越えてきた道のりと、未来への希望が溶け込んでいるようでした。
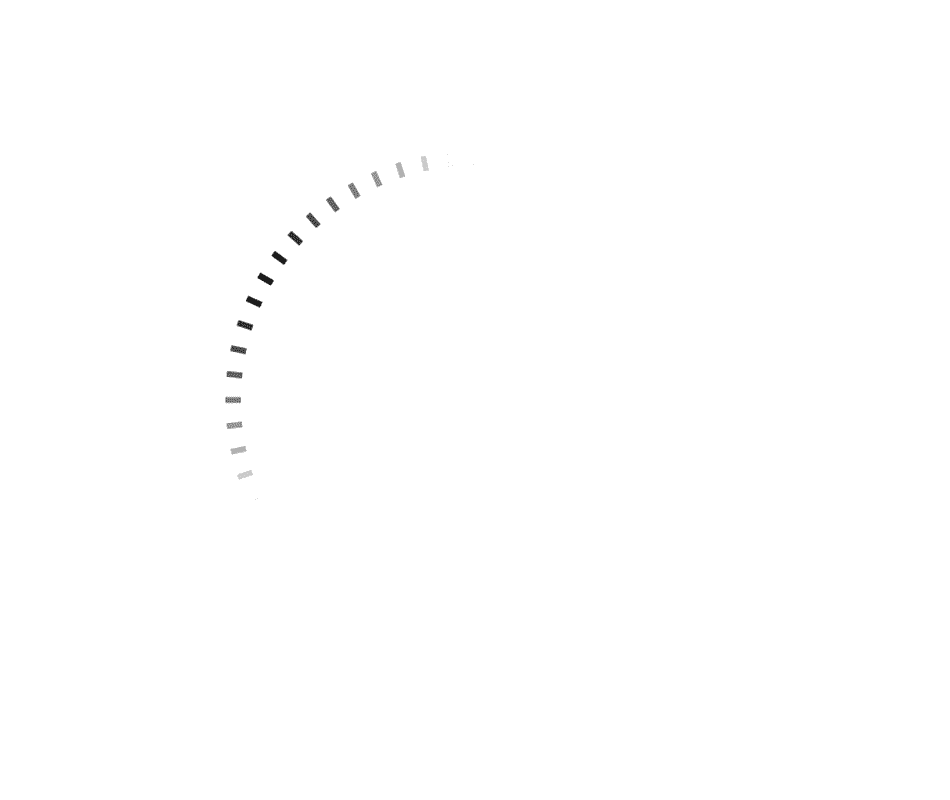
「まだまだこれからですよ」。
そう言って微笑む河合さんの表情は、どこまでも晴れやかです。
春、ゴールデンウィークの頃になると、蔵の目の前を通る道沿いに、少し色の濃い山桜が一斉に咲き誇るのだといいます。その美しい桜並木の先に、彼らが醸す酒の未来もまた、鮮やかに花開いていくのでしょう。岩木山の麓で生まれたこの一杯が、津軽の日本酒の新しい歴史を、これからゆっくりと紡いでいく。そんな確かな予感が、心を温かく満たしてくれました。
ギャラリー
今回の取材でお話をお聞きしたのは...

六花酒造
杜氏
河合貴弘さん
1970年北海道生まれ。東京のIT企業に勤務後、ものづくりへの情熱を胸に、妻の故郷・弘前へ。多くを語るより、ただひたむきに酒と向き合う実直な人柄で、巨大な蔵の片隅に置いた小さなタンクから研鑽を重ねた。その結果、全国新酒鑑評会での金賞受賞に加え、IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)2014でもゴールドを受賞するなど、技術は国内外で高く評価されている。
その信頼の深さは、取材時に北村社長が語った言葉が物語っている。後継者を問われ、隣にいる河合杜氏に穏やかな視線を向けながら、「酒を本当に知り、愛情を以て売る人でなければ、酒蔵の社長は務まらない。その思いを託せる人に引き継ぐため、この蔵を移したんだ」と、明かしてくれた。技術と人間性で蔵を支える河合杜氏の姿に、社長は六花酒造の未来を重ねているのかもしれない。